【単独インタビュー】『入国審査』監督コンビが語る“見えない壁”の恐怖
- Atsuko Tatsuta
スペイン映画として初めてインディペンデントスピリット賞で3部門にノミネートされた深層心理サスペンス『入国審査』が8月1日(金)に全国公開されます。

バルセロナからニューヨークに降り立ったカップルのディエゴ(アルベルト・アンマン)とエレナ(ブルーナ・クッシ)。移住のためのビザも取得し、新天地で暮らす準備は万全だったはずが、入国審査のカウンターで事態は一転。説明もなく別室に連行され、密室での不可解な尋問が始まる。なぜ二人は止められたのか?審査官は何かを知っているのか?予想外の質問が次々と浴びせられる中、やがてある質問によって、二人の間に予期せぬ波紋が広がる──。
監督・脚本を務めたのは、ベネズエラ出身で現在はスペインのバルセロナを拠点に活動するアレハンドロ・ロハスとフアン・セバスチャン・バスケス。自らの実体験をインスピレーション源に脚本を書き、わずか17日間で本作を撮影しました。
制作費65万ドルという低予算作品ながら、2023年のSXSW映画祭で上映され、第39回インディペンデントスピリット賞では新人作品賞、新人脚本賞、編集賞にノミネートされるなど、長編デビュー作ながら高く評価されました。
日本公開に先立ち初来日を果たしたロハス監督とバスケス監督が、Fan’s Voiceの単独インタビューに応じてくれました。

アレハンドロ・ロハス、フアン・セバスチャン・バスケス
──この映画はお二人の実体験から始まったと伺っていますが、どのように企画をスタートさせたのでしょうか?
バスケス 私たちは出会ったときからいつか一緒に映画を作りたいと思っていました。そして、二人に共通していたのが、国境に対する恐怖心でした。ベネズエラのパスポートを持っていた私たちにとって、どの国であっても入国審査はとても緊張感溢れるもので、恐怖心を喚起させる体験もあります。身近な人々の体験談も聞くと、私たちよりも厳しい経験をしている方がいましたが、今回は内側から湧いてきたようなストーリーでもあるので、リサーチする必要もほぼありませんでした。実体験を取り入れながら、有機的に脚本を書いていったのですが、結果的にはセラピーのような感じでもありました。
主人公たちは、“二次審査室”に連れていかれます。そこは狭間の空間で、米国に着いているけれど、入国はできていない。法律的にはどこにも属さないような場所で、誰にも知られず、審査官に尋問をされる。私にとってまさに最悪な悪夢のような体験でしたが、それを映画として描いたことにはセラピーのような効果がありました。
ロハス 二次審査室の緊張感と恐怖感。ずっと待たされ、そのうちに時間の感覚がどんどん狂ってくる。その感覚を(映画として)どう捉えるのかを何度も考えました。自分たちの経験に基づいて脚本を書くことは、興味深くもチャレンジングな体験でしたが、特に私は、二次審査室という部屋を描くことに興味ありました。あの特殊な空間からなるべく気を散らさないようにするべく心がけました。
ディエゴとエレナのバックストーリーを別々に描くのではなく、あの部屋の中の尋問を通して二人の背景が明かされていくような作りにしたいとは、初期段階から決めていました。二次審査室には第三者はおらず、カメラもない。扉の奥で何が起きているのか、誰もわからないような場所です。

──ニューヨーク、つまりアメリカを舞台にした理由は?ヨーロッパでも同様の経験をされたのでしょうか?
バスケス アメリカの入国審査は世界最悪だと思いますが、ヨーロッパも決して容易なわけではありません。どこから来たのか、どのパスポートを持っているのかで、状況は全く変わってきます。バルセロナに住むアメリカ人の友人は、ヨーロッパを始め世界のいろいろな地域を3カ月ごとに旅行していますが、スペインに再入国する時に尋問されたことは一度もない。ベネズエラ人にとって、これはあり得ない話です。ベネズエラ人が頻繁に出入国していたら、すぐに疑われてしまう。
私たちにとって一番大きな恐怖を象徴しているのがアメリカだったので、アメリカが舞台になっているのですが、ヨーロッパでだって同じようなことは起きます。今回エレナというスペイン人のキャラクターが登場しているのは、そういう背景からです。彼女はヨーロッパ人として当然の権利を主張し、尋問や不当と思える扱いに反発します。けれど、ついに彼女は、パートナーのディエゴが今まで彼女に言っていたことや、入国審査でこれまで彼がどういう風に扱われて来たのかを初めて実感します。
“壁を築く”ということは、アメリカだけでなくヨーロッパでも歴然とあり、スペインにも存在しています。私たちは、“国境”というコンセプト自体が過去のものであり、今は存在すべきではないと考えているんです。

──ちなみに、今回、初来日ということですが、日本の入国審査はスムーズにいきましたか?
バスケス とてもスムーズでした。僕らは今はスペインの市民権を取得し、スペインのパスポートで来日しているからということもあると思います。もしベネズエラのパスポートだったらどうだったのかはわかりませんがね。
今回はロンドン経由のフライトでしたが、もしベネズエラのパスポートだと、ロンドンを経由するだけでもビザが必要になります。まずバルセロナからマドリードに行って申請しなければならないし、お金も時間もかかる。来日するのももっと大変だったでしょう。日本はベネズエラに対してどれくらい厳しいのかわかりませんが、いくつかの国のパスポートに対しては、アメリカと同様に審査基準が厳しいのかもしれません。
──同じ人間でもパスポートによって入国審査で扱われ方が違うというのは、本当に象徴的ですよね。システム上仕方がないとはいえ、人間ではなくパスポートで判断される。
ロハス 本当その通りです。パスポートでもって人をコントロールしようとしているかのようです。二重国籍のように二つパスポートを持っていたからといって、二人の人間がいるわけではないにもかかわらず。

──先ほど、アメリカの入国審査が最悪とおっしゃいましたが、トランプ大統領はメキシコとの国境に壁を作ると主張するような方ですし、第二次政権になり、留学生ですら排除しようとしているというニュースまで流れてきます。この状況をどのように見ていますか?
バスケス 私たちが生まれた時から経験していることを、トランプ政権は実際に世界に詳らかに見せているようです。“問題あり”のパスポートを持っている私たちが、アメリカからどういう風に扱われるのかを、堂々と見せてしまっている。私たちが今まで話してきたことが本当だったんだと、今は世界に理解してもらえると思います。
トランプ政権のことを擁護する気はまったくありませんが、実は、アメリカの移民政策や入国制度は、彼が大統領になる前から最悪です。トランプになってから変わったわけではないし、今後も変わることはきっとないと思います。
もちろん、トランプ政権は段階を一歩進めてしまったようで、それはとても恐ろしいことですが。例えば、ベネズエラ人であるとか移民であるということ以外の理由もなく、強制送還されたり投獄されたりする。2025年に起きるべきことではないですよね。なので、僕らとしては『入国審査』という作品を通して、入国審査というプロセスの意味を改めて話すきっかけになったり、“みんな人間だよね”ということを再確認したりするきっかけになればいいなと思います。
──第二次審査に連れて行かれた時の不自由さと恐怖からは、映画『ミッドナイト・エクスプレス』(78年)を想起しました。自分の国を一歩出てしまえば、自分が常識だと思っていることが通じないことも十分あり得る。そうした現実を、エレナというキャラクターは象徴していたと思います。エレナは自分、あるいは自国の基準で主張を通そうとするけれど、その常識は通用しないことを思い知らされる。エレナの反応の変化はとても興味深かったです。
ロハス 私たちは“別室”に連れて行かれただけではなく、さらにその奥の個室にも連れて行かれたことがあるのですが、その時の恐怖や不安はトラウマ的で、今でも拭えません。
エレナというキャラクターに関してですが、ディエゴとエレナは愛し合っていて、一緒にアメリカに移住しようとしています。この二人の力学が重要だと私たちは考えました。ディエゴは私たち二人を反映したキャラクターです。ディエゴが受けたような尋問を、私たちは何度も経験しています。ディエゴは、怖いけれどとにかく何とかこの場を切り抜けて終わらせたいと思っている。けれど、エレナは少し違います。移民としての経験もないし、入国審査で尋問された経験もない。だから、一市民、あるいは一人の人間としての権利を主張するし、言いたいことを言う。それは当然の姿勢ではあるけれど、“尋問される”という、ディエゴがこれまで何度も経験してきたことを自分も初めて経験する。これが大事なことでした。

──ディエゴとエレナ 対 入国審査官という対立構造だけでなく、ディエゴとエレナの関係性の変化がこの物語の興味深いところです。ディエゴにはエレナに話していなかった過去があり、それは尋問の過程でエレナの知るところとなる。脚本の執筆過程で、どのようにあの要素を入れることになったのでしょうか?
バスケス 新天地に引っ越すあるいは移住をするときに一番大切なのは、身近な人と全てを分かち合うこと、正直であることだと思いますが、ディエゴは経験上、周囲からジャッジされることが何よりも怖い。だからエレナに話していなかっただけで、嘘をついたつもりは全くない。けれどもエレナとしては、この一つの“嘘”のせいで、彼が言うことを信じられなくなってしまう。
例えば、ずっと同じ土地で暮らしている場合は、10代の頃をどう過ごしたのか、どういう学校に通っていたのかといったさまざまな過去を、皆が知っている。けれども、移民の場合、新しい土地で自分が発した言葉が、彼らから見た過去のベースになる。だから、より言葉に重みが出てきます。たった一つの嘘から、すべての疑念が始まったりする。
もちろん、審査官たちは意図的に二人に亀裂を入れているわけです。しかも二人に対して、捜査官たちは違ったアプローチの質問の仕方をしています。これも人を操っているようなところがありますよね。この映画で見せたかったことのひとつです。

それと、ディエゴの叔父はアメリカに住んでいるわけで、二人が無事に米国に入国し移住できた場合、今度はエレナがディエゴに依存する立場になるわけです。
──この映画のような密室劇スタイルの作品では、会話が非常に重要です。リアリティのあるセリフをどのように書いていったのですか?
ロハス 二人のバックストーリーを時間をかけて作り紹介していくような構成を、最初は考えていませんでした。序盤ですぐに審査室へ二人が連れて行かれ、尋問を通してキャラクターが明らかになっていくという密室劇のスタイルがベストだと考えました。なので、説明的なセリフがまったくありません。実は、脚本にはト書きもほとんどありません。セリフだけで次々とページをめくりたくなるような、そんな脚本を目指しました。とても挑戦的なことではありましたが。
脚本はすべて一緒に書きました。コロナのパンデミック期に入ってからは、オンラインでGoogle ドキュメントで同じファイルをシェアし、一緒に作業をしました。実際にセリフを読んで、お互いにリアルに感じるかどうかを確かめたりもしました。

──ローラ・ゴメスが演じたバスケス捜査官は、明らかに移民系の人物です。このキャスティングは意図的だったのでしょうか?つまり、元々はアメリカにおいては“差別される側”だった移民系の人が、仲間といえる移民に対して厳しい尋問をするという構図は、意図的に作ったのでしょうか?
バスケス もちろん意図的です。まさに今おっしゃったようなことを狙ってキャスティングしました。かつては尋問される立場だった人が、国粋主義的な概念を擁護するような立場にもなり得ることを象徴しているキャラクターです。
私たちが実際に二次審査室に連れて行かれた時、私たちを尋問したのは、ほぼラテンアメリカ系の審査官でした。同じルーツを持っているであろう人にそういう扱いを受けることは、よりキツかったです。最悪ですよね。
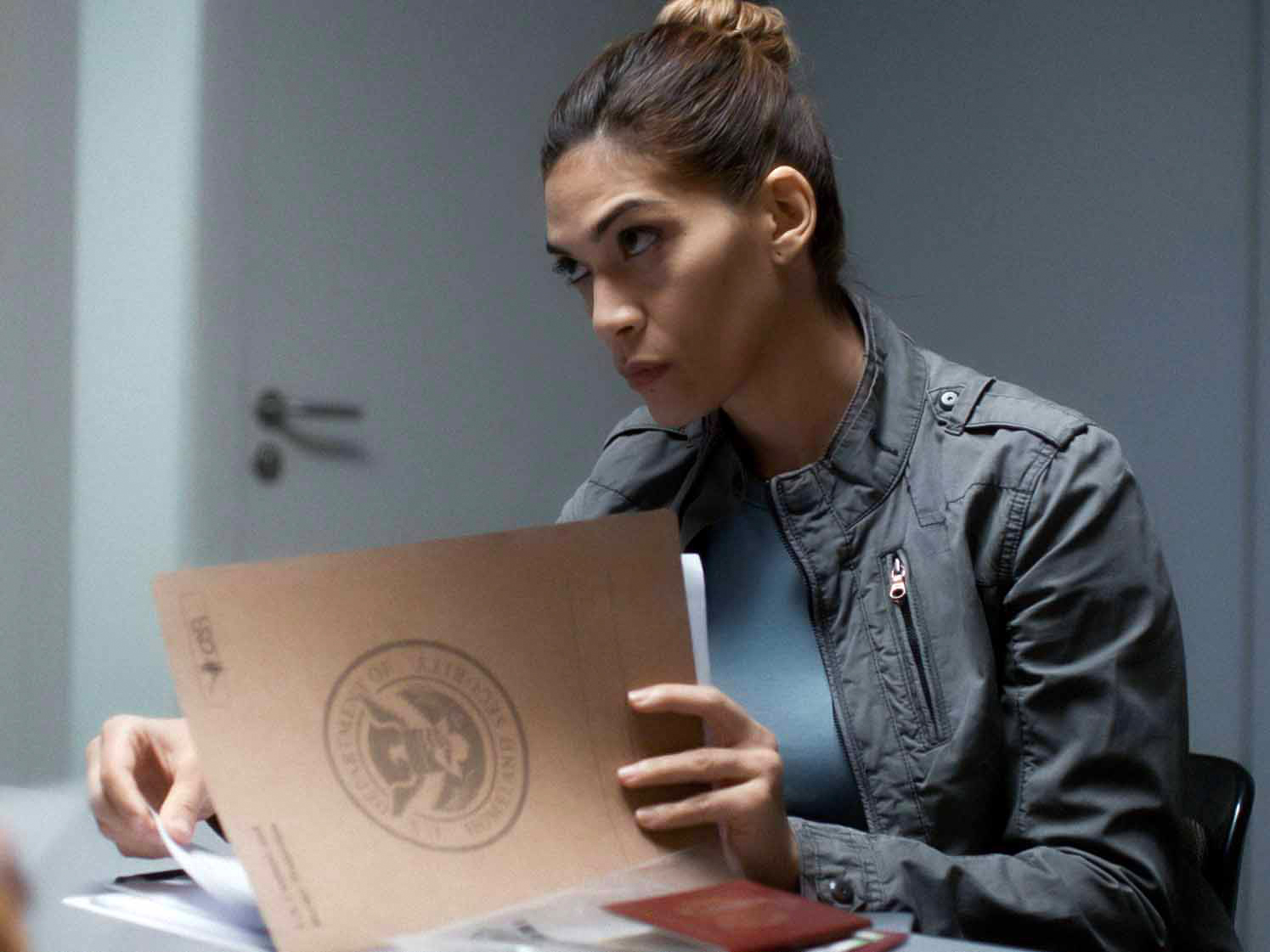
エレナはスペイン語で審査官の悪口を言いますが、バスケス審査官はスペイン語も理解し、“あなたたちの言っていることはわかっている”と威嚇しますね。これもリアルな体験から来たものです。ローラ・ゴメスはいとこが実際に入国審査官で、その方をベースにキャラクターを作り上げたそうです。あと興味深いのは、取材ではいつもゴメスについて聞かれること。バレット審査官(ベン・テンプル)も同じくらい差別的なのですがね。ベンがヨーロッパ人だからあまり触れられないのか。そのあたりも私たちにとっては考えさせられるところです。
==

『入国審査』(原題:Upon Entry)
移住のために、バルセロナからNYへと降り立った、ディエゴとエレナ。エレナがグリーンカードの抽選で移民ビザに当選、事実婚のパートナーであるディエゴと共に、憧れの新天地で幸せな暮らしを夢見ていた。ところが入国審査で状況は一転。パスポートを確認した職員になぜか別室へと連れて行かれる。「入国の目的は?」密室ではじまる問答無用の尋問。やがて、ある質問をきっかけにエレナはディエゴに疑念を抱き始める──。
監督・脚本:アレハンドロ・ロハス、フアン・セバスチャン・バスケス
出演:アルベルト・アンマン、ブルーナ・クッシ
2023年/スペイン/スペイン語、英語、カタルーニャ語/77分/ビスタ/カラー/5.1ch/日本語字幕:杉田洋子
日本公開:2025年8月1日(金)新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開
配給:松竹
後援:在日スペイン大使館、インスティトゥト・セルバンデス東京
© 2022 ZABRISKIE FILMS SL, BASQUE FILM SERVICES SL, SYGNATIA SL, UPON ENTRY AIE







