【単独インタビュー】『ひとりぼっちじゃない』伊藤ちひろ監督が描くホラーともいえる“片思い”
- Fan's Voice Staff
井口理(King Gnu)の映画初主演作として注目される『ひとりぼっちじゃない』が3月10日(金)に公開されました。

歯科医師のススメ(井口理)は、アロマショップを営む宮子(馬場ふみか)と出会い付き合い出すが、部屋に鍵をかけず、急に連絡がとれなくなったりと謎めいた行動の多い宮子に不安に駆られる。ある日、宮子の友人である蓉子(河合優実)から、宮子の身に起きた驚きの事実を告げられる──。
『世界の中心で、愛をさけぶ』や『スカイ・クロラ』など、多くのヒット映画やドラマの脚本家として知られる伊藤ちひろが、10年かけて書き上げた同名小説を自ら映画化した『ひとりぼっちじゃない』。近年では、“堀泉杏”名義で『ナラタージュ』や『窮鼠はチーズの夢を見る』の脚本を手掛けている伊藤ですが、本作は、数々の作品でタッグを組んできた行定勲監督がプロデュースを担っています。
主演は、King Gnuのボーカルとして活躍する井口理。謎めいた魅力を放つ宮子役に、映画『恋は光』や主演ドラマ『恋と弾丸』などの馬場ふみか、ふたりの関係に干渉してくる宮子の友人・蓉子役に、『PLAN 75』『ある男』『少女は卒業しない』など話題作に立て続けに出演し注目を浴びる河合優実と、豪華な顔ぶれが揃いました。
キャリアの新たな1ページを開いた伊藤ちひろが、初監督に込めた思いを語ってくれました。
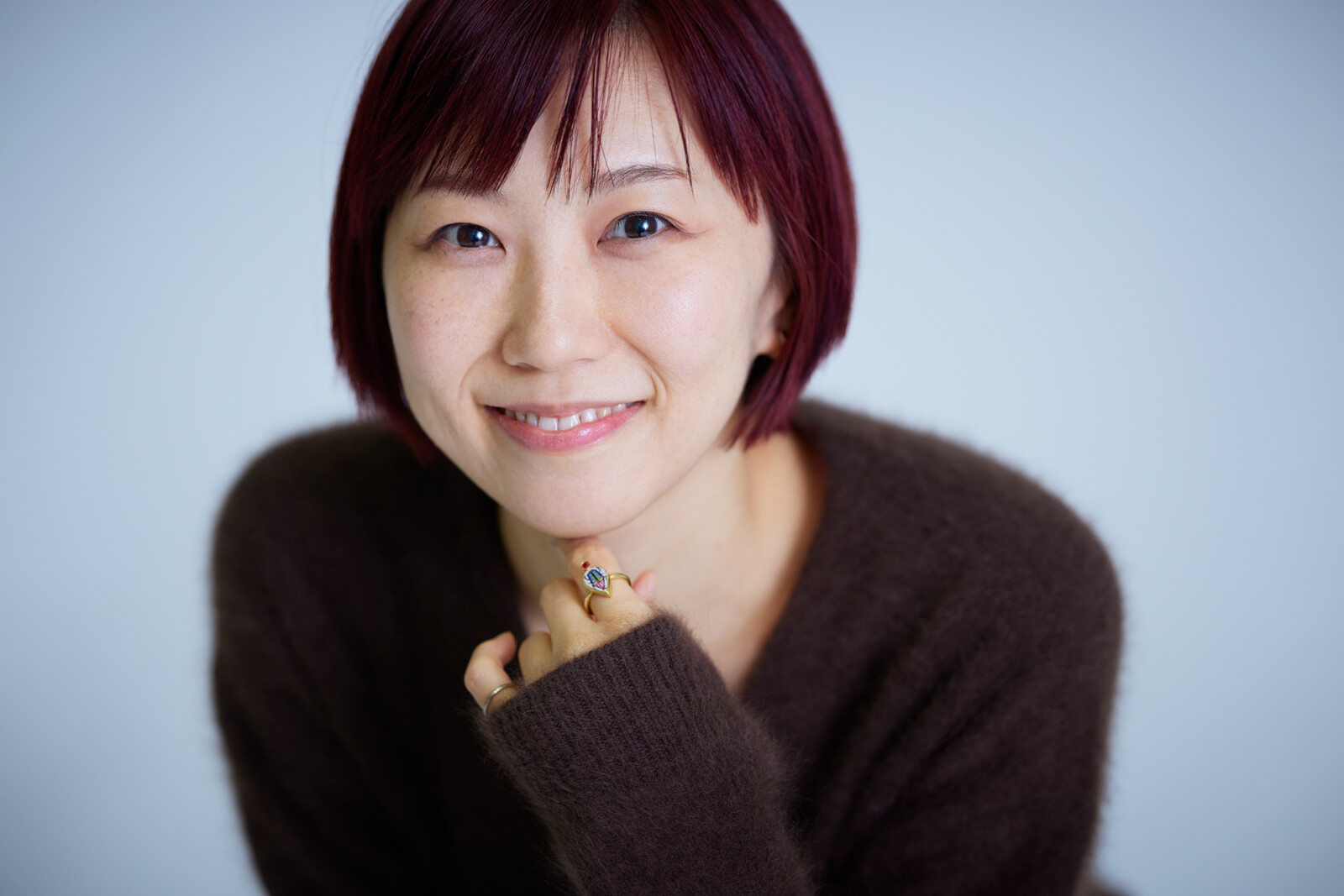
──脚本家として、行定勲監督の作品を筆頭に多くのヒット作や話題作を手がけられてきましたが、自ら監督をしようと思ったきっかけは?
『ひとりぼっちじゃない』の小説を書いたのが、大きかったと思います。この小説はものすごく長い時間をかけて書いたのですが、その間、ずっと一人の時間が多かった。実は私は小道具係の出身で、途中から二足のわらじで、脚本家としても仕事を始めて、だんだんと脚本だけにシフトしていきました。その頃から何となく感じていたのですが、あまり人に会わずに書いていると、自分の中での表現が鈍っていくような気がします。友人とか家族とか、自分の会いたい人だけにしか会わない生活がなんだか不健全に思えてきて、新しいキャラクターを生み出すための発見がなくなってしまうような、枯渇していくような感覚がすごくありました。そうした漠然とした不安がずっとあって、小説を書く中で、それがストレスになってきました。
主人公のススメは、自分のことについて考えこんでしまうキャラクターなのですが、それを日記形式で書いていたので、彼の考え方のようなものが、私の中に乗り移ってしまったところがあります。他人とどのようにしゃべっていたのか、どう感じていたのか、どうやって言葉を選択すれば良いのかなど、いろいろと見失いそうになった時期もありました。それで、人とコミュニケーションをとるのは大事だということを痛感し、撮影現場に戻りたいと思いました。でも、今さら小道具に戻っても、足手纏いになるだけ。それまでも、監督をやってみませんかというお誘いは受けたことがあったので、自分を変えるためにも挑戦してみよう、というのがきっかけです。
──それはいつ頃の話ですか?
小説は2018年に出版したのですが、その頃ですね。出版社の方からは2008年あたりにお話をいただいて、他の脚本を書きながら10年近くかかって書きました。
──初監督にあたっては、まず行定さんに相談されたのですか?
そうですね。行定さんとは同じ事務所(セカンドサイト)に所属しているのですが、監督をやってみようと思うと伝えたら、「事務所的には万々歳だ」と、社長も行定さんも喜んでくださいました。私にもっと前に出てほしかったみたいですね。脚本の時は、あまり目立ちたくない感じでしたので。

──あまり目立ちたくなくて、脚本家として「堀泉杏」というペンネームもお使いになっていたのですか?
私は小説を原作として脚本化する仕事が多いので、自分で小説を書くとなった時に、脚本家としての仕事は別の名前にしようと決めました。今回は監督するので、名前を全て統合して、また戻しました。
──ちなみに、伊藤ちひろさんが本名?
はい。ですので、堀泉杏という名前はもう使わないかもしれません。
──小説の「ひとりぼっちじゃない」は、日記形式で映画とはまったく異なるスタイルの語り口ですね。小説を書いている時は、映画化は想定していなかったのですか?
まったくなかったですね。
──では、その日記スタイルから、映画化に向けてどのように脚本を作っていったのですか?
小説を書いている時は、「きっとこの人は日記でこういう風に書いているけれど、傍から見たらそこまで不器用と思われていないかもしれないよな」などと、いろいろ思いながら書いていました。そういう時の気持ちとかを思い出しながら、脚本を書いていきました。
今回の脚本にはあまり時間がとれなかったのですが、最初に井口さんで当て書きしたことで、わりとスムーズに書けました。私は書くのがわりと遅い方なのですが、彼の存在からイマジネーションを刺激されて、いつもよりすごく書いていて楽しかったですし、早く書けました。もちろん、実際に早く提出しなきゃという焦りもあったのですが(笑)。

──なぜ井口さんだったのですか?
行定さん主催のお食事会で、ミュージシャンの方や役者さんやスタッフが集まっていたのですが、そこでご挨拶をしたことがあり、面白い人だなという印象が残っていました。行定さんの『劇場』にも出演されていますが、そのお芝居も良かった。なので、ススメ役を誰にしようかとなった時に、井口さんが最初に浮かびました。
──では脚本化する前に、すでに井口さんに出演を打診していたのですね。
はい。出演を前提に、まず原作を読んでもらいました。それから脚本を書いたので、理想的な形で進んだと思います。小説の感想を聞いた時は、ススメに対してひとりの人間として向き合い、まるでススメという人を知っているかのようによく理解してくれていて、自分と重ね合わせてくれたのだなという印象を持ちました。
──ポスターなどのビジュアルからは恋愛ドラマをイメージしますが、演出的にはホラー的なテイストもありますね。
この恋愛はススメの片思いなわけですが、片思いでは、相手の感情がわからない部分が多いですよね。思い合えていたら、お互いの気持ちもある程度すり合っていきますが、片方の思いが強かったりすると、付き合っていても相手の心が掴めない。誰にでも経験あると思いますが、例えば、相手と何日間か連絡がとれなくなると、いろいろなことを想像してしまいます。怖いことや最悪のことも考えたりしてしまう。私は、そういう恋愛に対する膨大なエネルギーみたいなものは怖いなと思います。自分自身が抱く感情としても怖いし、誰かからそういうエネルギーを向けられることも怖い。妄想の強さとか、恋愛の疑念とか。恋愛は、向かう方向によってはホラーだなと、日頃から思っています。だから、その雰囲気をそのまま映画にしたく、その怖さを登場人物の会話やストーリーで表現するというよりは、映画全体の雰囲気で表現したいと思いました。

──“片思い”と言われましたが、恋愛で基本的に“50/50”なことはないように思います。今回はススメの視点から見ているので、余計に彼の思いが強いように見えるかもしれませんが、二人は恋人とも呼べるわけです。でも、監督としては、これは“片思いの映画”として描いたのですね?
はい、片思いの映画という印象があります。ススメは少なくともそう思っていた。手ごたえを感じられていないというか、自分の言葉に対しての宮子の反応が薄いことが、彼をむなしくさせていたと思います。
──男性を主人公にしたのは何故ですか?
私は男性を主人公にすることが好きですね。女性の主人公に全く興味がないわけではありませんが、元々自分が読む小説も映画も男性主人公のものが好きですし、自分がオリジナルストーリーを書いたり作ろうと思ったときに、最初に面白そうだなと思うキャラクターは男性なことが多くて。
──それはご自分と少し距離があるからでしょうか?
そうかもしれないですね。でも、男性の方が人間的なキャラクターとして愛らしく感じられるのかもしれないですね。私は女子校に6年間通ったので、自分の中で女性に対する謎があまりないんです。女の人は知的だし、それを言葉に表現することが上手だと思います。男の人は、頭の良さがいろいろなものに隠されていて、ぼんやりとしかわからない部分がある。そういう部分を掘ってみたいという興味が、個人的には女性よりも男の人に対して強くあるのだと思います。

──宮子のような謎めいたキャラクターは、男性の作り手が女性に幻想を抱いて描く場合が多いような気がしますが、それを伊藤さんが描いているところが興味深いですね。
“男心ってこういうことかな”と思いながら、女の人を追いかけているような感覚で書きました。女性に対して夢は持っていないけれど、さすがに宮子くらい変わっていると、例えば同じクラスにいても、得体が知れないと思っているかもしれませんね(笑)。
宮子に対しての女性の評価は両極端だと思います。敵対するか、惚れてしまうか。
──宮子のモデルになっている人はいるのですか?
いませんね。こういう人がいたらミステリアスだし、きっと謎めいているだろうなというキャラクターを、自分の中で考えて作りました。“こんな人いない”と思って作り上げたのですが、小説を読んだ人からは、“私の周りにこういう人がいる”、“こういう人知っている”と結構言われるので、驚いています。私の周りにはいませんが。
──こういう掴みどころのない女性というか、かつてなら“ファム・ファタール”とも言われるような女性たちに惹かれるのですか?
私は、映画とか小説でも、謎めいている女性のキャラクターが好きというのはあるかもしれません。好きな本では大体、そういうキャラクターが出てくる。川端康成とか、吉本ばななさんの小説でも、少し謎めいた魅力的な女性が登場します。映画だと『青い夢の女』(00年)とか、デヴィッド・リンチの作品にもそういう魅力を感じます。

──ススメは井口さんの当て書きということでしたが、宮子はどうだったのですか?
私がイメージするところの、女性的で魅惑的な人。華奢なのに輪郭としては丸みがあったり、柔らかそうだったりする。綺麗な黒髪の人が良いなとは思っていました。
──黒髪には意味はあるのですか?
私の地毛が真っ黒ではないせいもありますが、真っ黒な艶のある髪に元々憧れがあります。黒髪には、神秘的で妖艶な感じがありますよね。魔力というか。馬場さんのルックスが以前から好きだったというのもあります。
──「魔力」でいえば、まさにこの映画の中にはそういうスーパーナチュラルというか、呪いだとかが登場します。これらのアイディアはどこから来ているのですか?
シンプルに私が好きなので。
──黒魔術が好きとかですか?
いや、それはないですし、怖い話もどちらかというと苦手です。けれども、生々しい現実をそのまま見るよりも、どこか世界観に怪しさや謎めている部分、不穏さがあるほうが、私の想像力が刺激されます。現実的な生々しいものは、普段の日常で十分に目にしているので。

──呪いや魔術といった要素を含んでいるにも関わらず、宮子の部屋はむしろ清涼感溢れる植物で満たされています。そのコントラストが面白い。デヴィッド・リンチの世界は、赤いベルベットのカーテンや絨毯といったインテリアがおどろおどろしい雰囲気を醸し出していたりしますから。
この映画ではキャラクターを家で表現したく、そこにはすごくこだわりがありました。宮子という人間は、境界線がないイメージ。家に鍵をかけない。窓も開けっぱなしで、ほとんど閉まっていることがない。外と地続きのような、理想は家に木が生えていて良いくらいの感じにしたかった。それと、あのように植物に囲まれて暮らしてみたいという憧れがもともとありました。
外からはわかりにくいが、実は宮子はすごく原始的で、たくましく、人間らしい人なんだろうなとどこかで思っています。
──俳優の方々の話し方が特徴的ですね。特に馬場さんは、意図的に抑揚をつけず単調に話しています。あの演出の意図は?
宮子はゆっくりと話すイメージがあります。馬場さんは本来ハツラツとした、明るい雰囲気の話し方をすると思いますが、宮子はどこか捉えどころのなく、こちらが一生懸命に聞こうとしないと聞き取れないかもしれないような、ふわっと儚い印象の声にしてもらいました。言葉自体がつかみきれない感覚になると良いなと思い。
私の脚本は元々セリフを最小限に抑えているものが多いのですが、特にこの映画はそうなっていますね。
──これは音声さん泣かせだったのではないかなと想像しました(笑)。
夏で、しかも窓を開けて撮影していたので、俳優の声よりもセミの鳴き声の方が大きかった。マイクを付けていますがかなり厳しかったので、アフレコもしています。
──気になったのは、心臓音のような音。あの音はどうやって録ったのですか?
編集の方が見つけてきてくれた音です。私は漠然と心臓音を使いたいと思っていたのですが、その方は子どもをもつ母親で、“胎内の羊水の中いた時に聴いたような音”を見つけてきてくれました。子宮の中にいるような気持ちになれる音。

──初監督ということで、演出に関してはどのように学んだのですか?
学んではいませんね。小道具や脚本で参加した作品で撮影現場に入っていたので、多くの監督の演出を見ていた、というだけです。感覚的というか、とにかく自分の思いを一生懸命伝えたという感じですね。私が未熟な分、周囲のスタッフが苦労したと思います。
──行定さんからはアドバイスを受けましたか?
監督の心得のようなものとしては、自分が“こうするんだ”と思った世界観を最後までブレさせないということや、スタッフとのコミュニケーションのとり方や伝え方について、いろいろとアドバイスをいただきました。行定さんはプロデューサーなので、スタッフ選びなどでは具体的なアドバイスをいただきました。
──監督としての資質は、お二人はかなり違いますよね?
違いますね。行定さんの作品の多くで脚本を手掛けているので、作風が似ないように気をつけているのかと聞かれることも多いのですが、もともとの表現者としての資質が違うので、そこはあまり意識していません。行定さんの方が、表現者として繊細でエモーショナルで、私はもっと淡白というか。
──行定さんは、伊藤さんの映画の特徴を「マジックリアリズム」という言葉で表現していました。非現実的なものを通してリアリティを表現したいという意図はあるのでしょうか?
ベタッとした現実をそのまま表現するよりも、ちょっと見えないはずのものが見えるというような、“気”のようなものを物語に取り入れるのは好きですね。
──目に見えないものの力という意味では、次の作品の『サイド バイ サイド 隣にいる人』にも共通点がありますね。
そうですね、『サイド バイ サイド』にはその要素がさらにあると思います。

──この『ひとりぼっちじゃない』は2021年の夏に撮影し、『サイド バイ サイド』は2022年の夏に撮影したそうですね。この二つの作品は関連性は?
企画自体は『サイド・バイ・サイド』が先でした。コロナ禍で撮影スケジュールが伸びてしまったので、せっかく集まったのでスタッフで作ろうと思って作ったのが『ひとりぼっちじゃない』でした。『サイド バイ サイド』はタイトルのまま、隣にいることの距離やコミュニケーションについての物語なので、私の中で意識はしていませんでしたが、そういう意味では通じているものがあるかもしれません。
──二つの作品を立て続けに監督してみて、いかがでしたか?
スタッフとか周りは苦労したと思いますが、私自身はものすごく楽しくて、自分の中で迷いなく好きだといえる職業です。私は一人っ子なので、あまりグループとか集団が好きではないし、個人主義の人間だと思っていたのですが、監督業では、限られた時間と予算の中でみんなで知恵を出し合ってひとつのものを作るのが楽しかった。今後も続けていきたいです。
Photography by Aya Kawachi
==

『ひとりぼっちじゃない』
出演:井口理(King Gnu)、馬場ふみか、河合優実、相島一之、高良健吾、浅香航大、長塚健斗(WONK)、じろう(シソンヌ)、盛隆二、森下創、千葉雅子、峯村リエ
監督・脚本:伊藤ちひろ
エグゼクティブプロデューサー:古賀俊輔、倉田奏補、吉村和文、吉永弥生
企画・プロデュース:行定勲
原作:伊藤ちひろ「ひとりぼっちじゃない」(KADOKAWA刊)
劇中映像:嶌村吉祥丸
製作:「ひとりぼっちじゃない」製作委員会(ザフール セカンドサイト ダイバーシティメディア ミシェルエンターテイメント)
制作プロダクション:ザフール
企画協力:KADOKAWA
日本公開:2023年3月10日(金)公開
配給:パルコ
公式サイト
©2023「ひとりぼっちじゃない」製作委員会







