【単独インタビュー】『対峙』フラン・クランツ監督が示す喪失の闇と一筋の光
- Atsuko Tatsuta
銃乱射事件の被害者家族と加害者家族による緊迫の対話を描くアメリカ映画『対峙』が2月10日(金)に日本公開されました。

アメリカのある高校で銃乱射事件が発生し、10数名が命を落とし、犯人の生徒も自殺。6年後、息子を失った悲しみから立ち直れないでいた被害者の両親ジェイとゲイルは、セラピストの勧めで加害者の両親リチャードとリンダとの面会に臨む。リチャードとリンダに責任は追求しないという約束のもとに始まった対話だったが、話が進むに連れて、ついにジェイとゲイルは、心の中にある疑念を口にする。犯行の予兆があったではないか。リチャードとリンダがそれに気がついていたら、事件は防げたのではないか──。
1999年に発生したコロンバイン高校銃乱射事件以来、同様の事件があとを絶たないアメリカ。『対峙』は、銃乱射事件の被害者の両親と加害者の両親が、事件の余波を受け止め、前に進むために、対面し話し合う「修復的司法」を題材にした人間ドラマです。それぞれ大事な息子を失った二組の両親は、事件によって破壊された人生をどう受け止め、生き抜くのか。リード・バーニー、アン・ダウド、ジェイソン・アイザックス、マーサ・プリンプトンという実力派俳優が顔を揃えた会話劇は、サンダンス映画祭でプレミア上映され批評家から絶賛、サン・セバスチャン国際映画祭では、若手審査員賞を受賞するなど高い評価を得ました。
TVドラマ、映画等で俳優として活躍し、本作で見事な監督デビューを飾ったフラン・クランツが、日本公開に際してオンラインインタビューに応じてくれました。

──2018年に米フロリダ州パークランドにあるマージョリー・ストーンマン・ダグラス高校で発生した銃乱射事件が、この映画を作る起点となったと聞いています。高校における銃乱射事件という題材では、マイケル・ムーアの『ボウリング・フォー・コロンバイン』(02年)やガス・ヴァン・サントの『エレファント』(03年)など高い評価を得ている映画がすでにありますが、この映画では被害者家族と加害者家族の対話という切り口で、事件の余波を描いている点がとても興味深いですね。このアイデアはどこから来たのでしょうか?
2018年にパークランドの高校での乱射事件のニュースを聞いた時は、大変ショックを受けました。ちょうど親になったばかりだったこともあり、現状と未来にとても恐怖を感じました。特に、トランプが大統領になったこともあり、アメリカはかつてないほど国が分断された状態でした。「憎しみ」が顕となり、人と人との繋がりを分断するような風潮に不安を抱いていました。
コロンバイン高校の事件から20年以上経っても、なぜこうした事件が全くなくなる気配がないのかといろいろ考えているうちに、もしかすると、この問題に対する我々の対応に間違いがあるのではないか、新しい別の入り口を見つけなければならないのではないかと思ったことが、この映画の入り口になりました。これまで考えてきた解決法とは全く違うやり方で、この問題に向き合う必要があるのではないか、と。
自分なりにリサーチをしたり本を読んだりするなかで「修復的司法」を知り、“これだ”と思いました。人は、実際に誰かと会って面と向かって話すことにより、ひとりの人間だと認識し、その人のことを知り、親密になることができます。そうなれば、対話が生まれ、私たちがこれまで解けていない問題が解けるのではないかと思います。
より大きなコミュニティの一員である意識をみんなが持つことは大事です。その中で自分の人生の体験や経験、哀しみも含めて人と分かち合えれば、何かが起こったときに、共感を持つことができます。

──具体的にはどのようなリサーチをされたのですか?
この題材に興味を持った時に、デイヴ・カリンの書いた「コロンバイン銃乱射事件の真実」という本を読み直しました。大学の同級生がたまたま彼を知っていて、本の出版イベントでお会いしたことがあったのですが、この映画の企画が動き出してから、話を聞いたりもしました。また、いろいろな方々に会って、リサーチを進めました。サンディフック小学校銃乱射事件をきっかけに銃規制を求めている「サンディフック・プロミス」という団体にもアプローチしました。
また、銃乱射事件だけでなく、車の事故や他のなんらかの形で家族を亡くした多くの方々から話を伺いました。どのように亡くした人を思い続け、胸の中に留めているのか。長い間、喪失と悲しみの中にいる方々の話を聞くことによって、悼むことの本質に触れられたように思います。そうしたリサーチの結果、この映画では、大切な人を亡くした時に、どのようにその死を悼み、喪失と向き合うのかを描くことにしました。
出来上がった作品には誇りを持っていますが、今は、撮影に入る前にもっともっと多くの方と会って話すべきだったかもしれないとも思います。リンダというキャラクターを作るにあたっては、コロンバイン事件の加害者の一人の母親であるスー・クレボルドさんからインスピレーションを受けました。ナンシー・ランザさん(サンディフック小学校銃乱射事件の加害者の母親で、事件で殺害された)も同様です。リンダ自体は、自分が読んだ色々な方たちを合成したキャラクターではあるけれど、もう少し関係者と話をできるように頑張ればよかったなと思っています。もちろん、もっと違うやり方があったのではないかと思う部分もありますが、初監督作品ですし、この映画がこういう形で認められて誇らしいです。監督として、脚本家として、本格的なキャリアを持てると信じられるようになりました。
──(“被害者”の両親の)ジェイとゲイルは、会合の会場となる教会の前に車で着いた時、まだ心の準備は出来ておらず、少し先のところで停車して、時間が来るのを待ちますね。その際に、草原のようなところの柵についている赤いリボンが印象的に映し出されます。この風景は、他にも4人の会話が激昂したシーンやエンディングでも登場します。この風景が表すものは何でしょうか?
まず、この物語のほとんどはひとつの部屋の中だけで展開します。事件のフラッシュバックなどを入れる気は、最初から一切ありませんでした。けれど時々、転機となる瞬間に、部屋ではない映像を入れたいと思っていました。
ゲイルとジェイは教会の先まで行って車を停めますが、そこに壊れた柵があり、修理用のテープが貼られています。この“壊れた柵”は脚本にすでに書かれていたものでした。ジェイにとって、この柵とテープは事件が起きた時に警察が張った立入禁止のテープを思い起こさせるものでした。彼のずっと脳裏にある風景。ある意味、あのシーンは、誰かを亡くした時の痛みのイメージとも言えます。

もちろん、あの風景の意味は観客の方が自由に解釈していただければ良いので、曖昧にしておきたいところでもありますが、私にとっては、キャラクターたちが哀しみをどう抱えて生きているのか、ということを象徴する風景です。なので、冒頭での柵のシーンでは、ジェイが怒りを内面に抱えていることを反映して強い光の中で、赤いテープが風で揺れ動いている。次にその風景が登場する時は、黄昏時で、風は凪いでいる。最後には、ライトが灯されます。解決したとは言わないまでも、なにか希望がもたらされたのかもしれません。
この映画は、人の心の内を描いています。私は、大切な人を亡くした時の悲しみは、決して消えることはないと思っています。悲しみは、ただ、心の中で何かに変化していくだけです。
──コロンバイン高校の事件後、高校の柵に犠牲者たちを追悼するためのリボンが結ばれましたが、そこから来たイメージではないのですね?
はい、コロンバイン高校のことは考えもしませんでした。それはまったくもって偶然です。実は、あの柵はたまたまロケハンした時に見つけて、赤いリボンのようなものは、測量テープでした。私たちが持っていたイメージにぴったりで、まるですべてを表現しているようだと思いました。数日後、撮影に訪れた時にもまだ柵にテープがあったので、そのまま使いました。このシーンはアメリカ的な風景にしたく、昔のウエスタン風というか、寂れた感じの、風化していくような風景を求めていたのですが、それにぴったりの場所でした。テープが測量テープだったことも気に入っています。まるで今の社会を測り直さなければいけないのだ、という風にも思わせてくれるからです。意識はしていませんでしたが、コロンバイン高校の柵は、当時見たことがあったかもしれないので、もしかすると潜在的に何かを感じていたのかもしれませんね。
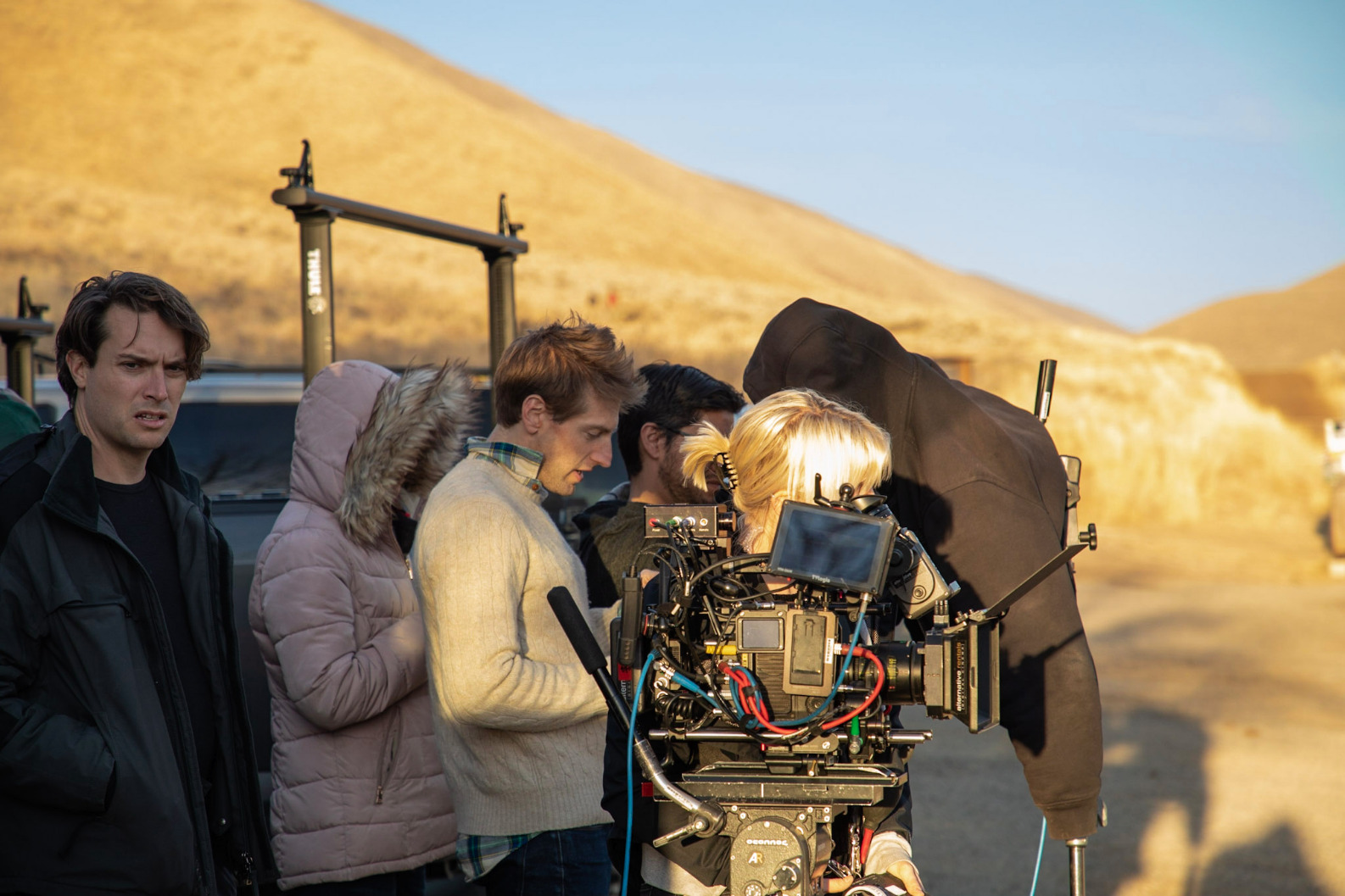
──会合の場所を教会に設定した理由は?
私はキリスト教徒の家庭で育っています。とは言っても、敬虔なクリスチャンというわけではなく、今は教会に通ったりもしていませんが、慣れ親しんだ場所ではあります。
会合が開かれる場所は、最初からスピリチュアルな場所にしようと決めていました。南アフリカの「真実和解委員会」からの影響ですね。大学時代にデズモンド・ツツの本を読んでいたのですが、今回の脚本を構想中に思い出しました。アムネスティが聴聞会を開いて、被害者と加害者を対話をするという場を持ったのですが、罰するためではなく、前向きに人生を進めるためのものでした。これは裁判所では出来ないことです。
暴力や死、悲しみ、悼む気持ちは、人間にとってとても大きな感情です。これらは、スピリチュアルな体験でもあり、そういう場に置かれたら、人生の意味を考えざるを得ません。必要なのは、信じること。人によっては信仰かもしれません。この作品における4人は、精神的な葛藤をお互いが理解しようとします。そうしたスピリチュアルな体験をする場所として、教会に併設されているスペースであることに意味があると思いました。教会のチャペルでは、重すぎますからね。

──4人の対話のシーンに音楽はありませんが、冒頭ではチャペルで子どもがピアノを練習し、最後には聖歌隊が練習している賛美歌が聞こえますね。
この教会の建物の構造は、とても重要なものでした。チャペルがあり、階下に部屋があり、その横にはまた会合などで使える部屋があります。この部屋は宗教的というより、もう少し一般的なものです。なので、ちょうど良いと思いました。手を伸ばせば、神──つまり信じるものがすぐそこいるというところを見せたかったからです。
上の方から聖歌隊の歌が聞こえるというのも良いなと思いました。ラストでジェイソン・アイザック演じるジェイはその歌声に反応しますが、それは神を見つけたという反応ではありません。自分の人生の中にスピリチュアルなものが欠けていたのだと気づいた瞬間です。愛する息子を喪った痛みや悲しみと向き合う中で、彼はスピリチュアルな部分を失ってしまっていたのです。
私はあの会合が開かれた部屋のことを、ふざけて“神の隣(God-adjacent)”と呼んでいました。部屋には、確かに十字架がありましたね。ジェイは、最初にあの十字架を見て揶揄しますが、どんな神であれ、あるいは神でなくても、人にとってスピリチュアルな存在は必要だと私は思っています。ちなみに、あの十字架は外して撮影しようと思ったのですが、教会から許可されませんでした。

──見事な初監督作品ですが、以前から監督業には興味があったのですか?
はい、監督業にはずっと興味がありました。実現するまでに30年以上かかってしまいましたがね。10代の頃はビデオカメラで映像を撮っていましたが、20歳くらいから演技に夢中になってしまい、最近になってまた作り手の方に戻って来た、という感じでしょうか。人生経験を積み、成熟し、自分のビジョンを持って、多くの人と協力して作品を作る。これにはある程度の時間と経験が必要だったと思うので、やはり今がそのタイミングだったのだと思います。
==

『対峙』(原題:Mass)
監督・脚本/フラン・クランツ
出演/リード・バーニー、アン・ダウド、ジェイソン・アイザックス、マーサ・プリンプトン
2021年/アメリカ/英語/111分/ビスタ/カラー/5.1ch/G
日本公開/2023年2月10日(金)TOHOシネマズ シャンテほか全国公開
配給/トランスフォーマー
公式サイト
© 2020 7 ECCLES STREET LLC







