【単独インタビュー】深田晃司監督、新作『よこがお』を語る

- Atsuko Tatsuta
浅野忠信主演の『淵に立つ』(16年)でカンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞を受賞するなど、日本を代表する若手監督のひとり、深田晃司。長編第7作目となる『よこがお』(19年)は、『淵に立つ』でも重要な役を演じた筒井真理子を主演に起用したサスペンスフルな心理ドラマです。
訪問看護師の市子は、献身的な仕事ぶりと温厚な人柄で周囲からも信頼されていた。訪問先の大石家のふたりの娘、基子とサキの勉強もみてやるなど、仲もいい。だが、甥がとある事件を起こしたことで、マスコミから追われるように……。
思わぬ出来事により、すべてを失っていく女の転落を描く衝撃作『よこがお』は、8月にスイスで開催されるロカルノ国際映画祭のコンペティション部門にも選出が決まったばかり。7月26日(金)の公開を前に、深田晃司監督に製作の裏側をお聞きしました。

──『よこがお』は2016年の『淵に立つ』が終わった頃から、企画が始まったそうですね。
そうですね、『淵に立つ』の企画プロデューサーの方から声をかけていただき、筒井真理子さん主演で新しい作品を撮ろうと決め、そこから脚本開発がスタートしました。
──写真で見た筒井さんの横顔が美しかったことがそのきっかけとのことですが。
朝日新聞に筒井さんのインタビューが掲載されていて、そのときの写真が窓を向いている横顔で、ガラスに反射していてとても美しかった。筒井さんの横顔はいいものだなと、改めて思ったんです。そういうきっかけで、女性の話として脚本を書き始めたけれど、書いていくうちに、物語の内容が仮タイトルでつけていた“よこがお”に合ってきた。タイトルに引きずられて、物語の内容ができてきたというところがありますね。

筒井真理子演じる市子
──『淵に立つ』でも一緒に仕事をされていますが、筒井さんの女優としての魅力はどこにありますか?
卓越したセンスも技術もありながら、それだけに頼らないで、撮影に向かってきちんと準備をしてくる。全身全霊で演技にぶつかってくるところですね。例えば、台本にびっしりと書き込みがしてあり、例えば、訪問看護師を演じるにあたっても、スタッフの取材に同行されるし、ひとりで実際に訪問看護師の仕事場についていって、取材したり体験したりもしていました。役のつくりこみのために妥協しない。素晴らしいですね。
──『よこがお』での筒井さんは、とても内省的といいますか、演技がとても自然で、控えめな表現をされる。だからこそ、深みがあり、見入ってしまうようなところがありますね。スクリーンでずっと見ていると、どんどん彼女の世界にはまっていくという不思議な魅力があります。
技術的には長けている方なので、オーバーな演技というか、輪郭のくっきりした演技もできる。今回は、私の作品ということで、合わせてきてくれたと思います。でも、筒井さんの本来の資質は、この作品に観られる演技寄りだと思いますね。ものすごい準備をしながら、カメラの前になるとそれを忘れることができる。そこがすごいことだと思いますね。

──脚本を書く上で、最初のアイデアはどこからきたものですか?
映画を作る度に、いつも出来上がってしまうと、起点ってなんだったのかなと分からなくなるんですけど……(笑)。企画プロデューサーの方が、こういう物語はどうだろうと提案してくれたのが、女性3人の物語だったんです。『めぐりあう時間たち』(02年、スティーブン・ダルドリー監督)のような。それで、自分なりに書き始めたんですが、市子と基子の関係が出来上がっていく中で、筒井さんにフォーカスした物語にしようと自然になっていきました。
──この物語は、誘拐事件が起こるわけですが、この事件をめぐる3人の女性の物語として書き始めたのですね。
そう構成していましたね。
──市子は、メディアの行き過ぎた取材や報道によって、運命を狂わされていきますが、メディア批判的な要素と言えるアイデアはどこからきたのでしょうか?
よくも悪くも、映画には作り手の世界観がそこには反映されるし、反映されるべきだと思っているんですよね。でも、最初から、メディアスクラムとかメディアの暴力性を描くつもりはありませんでした。あくまで市子という登場人物がもつ社会性を剥ぎ取られていく、と考えていった中で、当然、ああいう事件が起きたらメディアが来るだろうという感じで、考えていったものです。メディアの描かれ方は、僕自身のメディアへの視線と重なっている。一方で、自分自身が映画をつくることで、世間を知っていくという側面があります。大きな犯罪が起こると、被害者家族だけでなく、加害者の家族もたいへんなことになるとは思っていたんですが、今回、いろいろ調べてみて、夫が犯罪を犯すと、妻にもメディアが殺到するとか、近隣住民にまで取材が及んで、その場所にいられなくなり、引っ越すとか、家を失うとか。そういったことが起きている。ルポルタージュを読んだり、取材をしていく中で知って、最後は固まっていったという感じですね。

市子と市川実日子演じる基子(右)
──また、基子には、特別な感情がある。それが叶わない腹いせに、マスコミに衝動的に話したことが、思わぬ騒ぎを起こしてしまうわけですが、このような“人の口”、メディアの最もプリミティブな形でもあるわけですね。つまり、メディアと人という関係がさまざまレイヤーで描かれていて、いかに人の感情や運命を左右していくかというドラマが興味深かったです。今回は、また同性愛という今日的なテーマも含んでいますね。
市子と基子は、じゃあ、どう接近してくのかと考えたときに、基子が市子を好きになったらどうなんだろうと考えました。そうなると女性同士の関係になるんですが。脚本を書くときに僕が心がけているのは、登場人物の性別を考えないということ。女性だからこうするとか、この人が男性だからとかあえて意識的に考えないようにしています。そうすることで、自分の中にある男性らしさ、女性らしさのステレオタイプの観念からちょっと距離を置くことができる。LGBTは、社会問題として扱いたいわけじゃないんです。当然、社会には同性愛の方もたくさんいます。なので、男女の恋愛と同じように、女性同士の感情の交換も当たり前のものとして描きたかったんです。本質的には、人を好きになることの難しさ。それは、辰男が、サキという女の子に一目惚れしたか、可愛いと思ったことで事件を起こしてしまった。それは市子にとっての婚約者との関係性とか、人を好きになることが、人と人との溝を顕にしてしまう。そっちの関係性のほうが大事で、男性であるか、女性であるかは重要だと考えていなかったですね。

──強い感情は、凶器にもなりますよね。歯車が狂い出すと。
そうですね、古今東西、昔からそうですよね。人間の感情は怖い。
──この作品では、男性の存在が希薄ですね。市子の婚約者で基子の恋人の和道、事件を起こしてしまう基子の甥の辰男。女性にフォーカスした映画をつくりたいというのはあったのですか?
最初に筒井真理子さんの映画をつくるというところからスタートしたのが大きいかなと思います。あえて、女性にフォーカスしようとしたわけではないけれど、でも、僕のつくる映画はそうなる傾向があるようですね。女性か男性かと意識していないんですが、どこにカメラを向けたいかということになると、それは女性になりがちなんです。映画を撮ることによって、知らないものを知る。それが表現だと思っていますが、何を被写体にするとなると、自分にとって遠い存在の女性の方にカメラを向けようという原動力になるのかな、と思います。

須藤蓮演じる辰男(左)
──女性映画といえば、ハリウッドでもジョージ・キューカーやダグラス・サークなどの作品がそう呼ばれてきました。日本映画の黄金期にも、小津安二郎や溝口健二、成瀬巳喜男などの名匠が女性を主人公にさまざまな名作を残しています。深田監督は、最近の日本では数少ない、女性をまっこうから描く監督ですよね。
女性映画っていうことでいえば、女性映画という言葉でとくくられること自体が、もしかしたら間違っているかもしれないですね。尊敬している作家の富岡多恵子さんは、フェミニストの代表的な作家のひとりですが、60年代くらいのエッセイで、女流作家という言葉自体に拒絶反応を示していて、上野千鶴子さん(と小倉千加子さん)と「男流文学論」と題した鼎談をしていたりもするんですが、でも、女流作家というのが嫌だと書いている本の帯に、“気鋭の女流作家”とか書かれていて、まったく空気読まない編集者だな、と(笑)。まあ、それほど女性で小説家というのが少なく、文壇も男性社会であったからなのでしょうけど。
映画界も最近は女性が増えてきていますが、まだまだ少なく、50:50ではない。女性監督や女性映画という言葉が死語になるようほどに、増えればいいんだろうなと思います。一方で、今回の映画をつくる上で、なんとなく意識していた映画のひとつは、溝口健二監督の『西鶴一代女』。ものすごい大傑作なので、こういうのもおこがましいんですけど、女性の流転を淡々と描いていくところに惹かれて、今回『よこがお』を作る際に意識していました。溝口監督の映画では、女性が可愛そうな立場に置かれることが多い。ただ恋をしただけで、最後は磔にされてしまうとか。『西鶴一代女』とかでも、高貴な立場から流転して、風俗に身をやつしていく状況が描かれている。これは、文学でも共通していること。僕が以前に映画化したバルザックの「ざくろ屋敷」もそうですが、恋に破れて病で死んでいってしまう女性とか、そういったものが描かれていたりする。それは、男性社会の中での女性のはかなさが、文学的なもののひとつの魅力としてなっているという面もある。それ自体がもしかしたら、フェミニズムの観点から問い直されるべきことなのかもしれないんだけど。
ただやっぱり、それなりの理由もあると思うんですね。現実として、日本社会の中で女性が弱い立場であったことは間違いないことですから。今のような過渡期では、フェミニズム的視点から、(映画で)強い女性を描くことで男性社会とのバランスをとろうとしているというところもあると思うんです。何千年も男性社会の中で、やっと100年程度前からフェミニズム運動が進むなか、バランスを取ろうとするのは、ありだと思います。僕自身もマーベル映画が好きで、『キャプテン・マーベル』(19年)とか強い女性が描かれていて面白いと思ったりしています。DCだけど『ワンダーウーマン』(17年)もありましたし。
──『キャプテン・マーベル』は、強すぎるほどですがね。
あれはパワーバランスを崩しているともいえますが(笑)。あれっ?この人ひとりいたら、勝てるんじゃない?と思いますからね。まあ、『アベンジャーズ/エンドゲーム』も最後に女性ヒーローが勢揃いしてスパイダーマンを守るとか、そうやって女性のほうが当たり前のように強いと描いている。
でも、男女平等って女性の強さを強調することばかりではないと思うし、現実問題として、2019年においても社会的には女性は弱い立場にあると思います。医大の入試で、女子学生の点数がマイナス10点になっていたとか、そんな暴力が平気で起こっているんですから。その時代に、女性を男勝りという意味でのかっこいい女性に描くことばかりが突出すると、ある意味、ガス抜きになってしまう。暴力の被害を受けやすいのも女性である、という現実を反映しないものになってしまうと感じています。だから、溝口健二やジョン・カサヴェテス監督の『こわれゆく女』(74年)とかもそうですが、社会の中での女性の危うさをありのままに描こうとすると、そういう女性の弱さにフォーカスをする描写がどうしても増えてしまう。僕は、マーベルものも観るのは大好きなんですけれど、自分が描くときには、強い女性をどうだとばかりに描くことには関心がもてないですね。
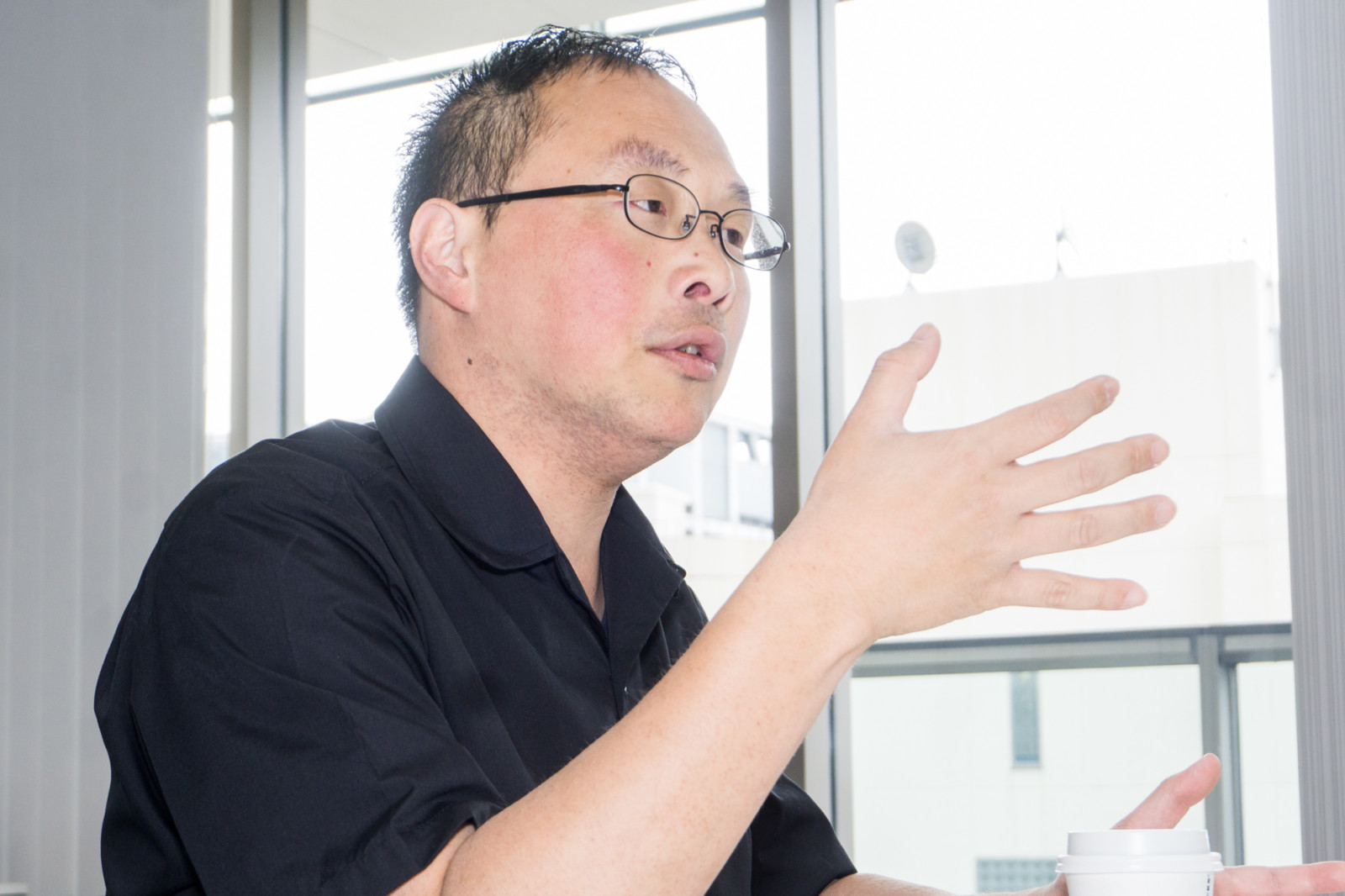
──市子やサキは、女性の弱い立場を体現していますね。サキは被害者なのに、その後周囲の噂などで二次被害を受ける。市子もマスコミの攻撃などから仕事を失い、社会的な助けはなにも得られない。これは、かなり現実的ではありますが、悲観的ともいえますが。
『東京人間喜劇』(08年)という作品を作ったとき、女性がひどい目に遭うんですけど、観客の人から、”監督、女性のこと嫌いですよね”と、まるでミソジニーみたいに言われた(笑)。でも、僕としては、映画の中で、女性も男性も等しくひどい目に遭わせていると思っているんですけどね(笑)。
──『よこがお』の脚本を書いていて難しかったところは?
構成ですね。二重構造になっているところ。ミラン・クンデラの「冗談」という小説にインスパイアされたところがあるのですが、観客からも想像力を引き出したいし、毎回作品ごとに違うのですが、今回は、最初の10分くらいは、筒井さん演じる女性が何をしている人なのか、よくわからない形にしたんです。市子とリサがどういう関係なのかをどこで観客にわからせるか、というところが苦労しました。脚本でも苦労し、編集でも苦労しましたね。
──クンデラとも、人間の闇や悪意という部分に踏み込んでいくといった共通項がありますが、日本では、悪人は描かれるけれど、普通の人、善良な人の悪意や闇に踏み込む勇敢な監督は、あまり多くないですね。
社会的に道徳性を求める部分がありますからね。事件が起こると、動機を求める。自分たちは、犯罪をおこさない人間である、と思いたがるという部分があるから。日本の物語でいやだなと思うのは、犯罪者の動機や原因を描こうとする。子供時代、いじめられていたから、とか。でも、本来、明確な答えってわからないと思うんですよね。19世紀と20世紀、ここ200年くらいで人間観は大きく変わったと思うんです。19世紀以前は、人間は、自分自身を抑制しコントロールできると思っていた。だから、コントロールできなくなると、悪魔に憑かれたとかとされていたわけですが、ユングやフロイトが無意識という領域を発見したことによって、それ以降は、どんな人間でも自分のことを完全にはコントロールできない、無意識の領域の影響を受けながら行動している(といわれるようになった)。そういう人間観からいくと、ひとつのトラウマに原因づけたりするのは、人間理解において危険なことだと思っています。そこに気がついていると、あいまいにならざるを得ない。ミステリーは、答えがないとミステリーにならないわけで。そういうミステリー的な構造にはしたくないというのはありますね。
──今回のラストは、最初から決めていたのでしょうか?
実は、脚本の改稿を重ねるなかで、最後の最後に決まったシーンなんです。決定稿で。それまでは違う展開で書いていました。小説版はそのラストになっていて、市子と基子の物語をラストに向けて語っています。(映画では)そこをばっさり切って、ああいうラストにしました。それは、音で市子の感情を表現するというアイデアを思いついたので、映画のラストはあのようなかたちになりました。ドラマではなくて、視覚的なものや音という映画ならではの表現方法で。

──筒井さんは女性ですが、筒井さんとはどのような会話をされたのでしょうか。
筒井さんは、面白い脚本だと思った後に、これを自分が演じるのはたいへんだと思ったとおっしゃっていましたが、あんまり市子の感情面などについては話しませんでしたね。それが答え合わせのようになってしまうと面白くないので。あくまでも映画は脚本がすべてで、その脚本をどう解釈して(演技によって)俳優が見せてくれるのかが、監督と俳優の共同作業だと思っているので。質問にはもちろん答えますが、そんなに議論することはないですね。
市子の“復讐”とはなんなのか、ということについては、筒井さんご自身は復讐のようなことはしないタイプだとおっしゃっていたし、普通はしないかと。
──確かに、基子の口から復讐という言葉が出たときには、ちょっとひっかかりを感じましたね。
予告編でも登場していて、ある意味キーになっているんです。
ストレートに復讐という言葉が出てくるわけではなく、市子自身もちょっと間をおいて、考えてから、疑問形で言っています。市子も、自分自身がやったことがなんなのか整理できていなくて、言葉にしてみたら、復讐というある意味チープな単語になってしまう。結局、復讐を成し遂げることが、重要なわけではなくて、いろいろなものを失った彼女が唯一、人生を進めていくために復讐というものがあった。それも誰にもダメージを与えることがなく、空回りに終わってしまう。
──すごい残酷な結末ですね。監督厳しい。
そうですね。まあ、でもそれが人生ですよ。なにか事件を起こしたとき、犯人にはっきりした動機があるかどうか、あやしい。取り調べを受ける中で、言葉にさせられていく。そのなかで、ああかもしれない、こうかもしれない、という言葉を見つけ出して、しゃべると犯人自身の告白として記録され、動機になってしまう。でも、本人にさえ、動機はわからないもの。本人がそうだと思ったとしても、そうかどうかは疑問です。
──そういう意味で、この『よこがお』という作品は恐ろしい作品ですよね。
ありがとうございます。そういっていただけると。Twitterでも、“血が一滴も出ないけど、ホラー映画より怖い”と書かれました。

──日本人の人間性善説。映画にもありますね。ラース・フォン・トリアーとかミヒャエル・ハネケとかは悪意の監督とかいわれてしまう。嫌な奴という人もいますが、私には、誠実に人間の本質を見よう、映像化しようと努めている誠実なクリエーターに見えます。深田監督もそういう闇の部分に踏み込むことに躊躇しないですよね。それくらい、誠実に人間に向き合っているというか。
ラース・フォン・トリアーやミヒャエル・ハネケといった監督もたぶん、そうだと思うんですが、露悪的にやろうとしているわけじゃないと思うんですよね。いい人を描かないことで何を言われても、僕は気にしてないですが、宣伝の方が気にしているかもしないですね(笑)。
──資金繰りにも影響ないですか。
それは影響あると思いますよ。でも、高いバジェットでつくる映画ではないんですが。アイドルが出てくるわかりやすい映画でもないし、こういう企画に角川さんが賛同してくれたというのが、ありがたいですね。そういうものをコツコツつくり続けて、自分がつくりたいものをつくる土壌をつくり、観てくれる観客を一緒に増やしていければなと思います。
──でも、妥協はしない?
していないですね。でも、これも無名のキャストだけでは撮れないですね、映画はお金がかかる表現なので。面白いのは、ゴダールの『ウイークエンド』(67年)で、ある女優の撮り方がひどいんですよ。ひたすら逆光で、ぜんぜんきれいに撮っていない。あとでゴダールのインタビューで、プロデューサーから押し付けられた嫌いな女優だったから、あえてそう撮ったと話していたのを読みました。そういうプロデューサーとのせめぎあいみたいなものは好きだな、と(笑)。
──美容師の和道を演じた人気俳優の池松壮亮さんのキャスティングはどのように?
キャスティングしてから、『だれかの木琴』(16年)で美容師役を演じていたことを知って、しまったと思ったんですけど(笑)。最近では、石井(裕也)監督の『夜空はいつでも最高密度の青色だ』(17年)を観てもすごくいいなと思っていた俳優だったので、お願いしたいと思いました。和道というキャラクターは、もともともうちょっと幼い、チャラチャラした感じの設定だったのですが、それだと厚みがでないな、どうしようかな、と思っていたときに、池松さんをキャスティングするというアイデアが浮かび、それなら僕がもっていない和道像をつくってもらえそうだ、と。ご本人の精神年齢の高さというか、落ち着いている、大人びた感じが、和道というキャラクターにも反映されて、筒井さんとのやりとりにも、あまり年齢差を感じさせない、大人同士の関係になりました。

池松壮亮演じる和道(右)
──彼は、日本大学芸術学部映画学科の監督コースで学んでいましたね。撮影をしながら、やはり作り手側のことを学ばれているところはありましたか?
なんかあったかなあ。現場を静かに観察される方だなというのは感じましたね。こっち側の匂いがするというか。我が強くないですよ。俳優さんによっては、作品をよくするためにというより、自分の爪痕を残すために、あの手この手を加えて来る方もいる。池松さんの場合は、この役に収まることが大事で、目立つことが大事じゃないという。この世界観の中で生きることを意識されている。そういうことができる俳優は、作り手としての意識が高い方が多いですね。自分のスタイルはもっていますけれどね。
──演技スタイルは、柔軟なタイプなんですか?
柔軟かどうかは、もう1、2本一緒に仕事しないとわからないですね。また出ていただけるなら、ぜひ一緒に作品を撮らせていただきたいですね。

──監督自身、この映画を通して何か新たに発見したものはありますか?
いままでの過去作と比べても夢のようなシーンが多いんですが、映像の面白みを改めて感じましたね。脚本に夢とか幻想のシーンと書かれていても、映画を撮る上では、ただ単にカメラの被写体であるので、すべて等価なんですね。だからこそ、編集の段階では、夢や幻想のシーンの使い方は面白くて。今回は、とくに現実と夢や幻想のシーンをすべて同じトーンで描いたので、そうなると夢や幻想のシーンが、どんどん他の現実のシーンに影響していく。それを自分的にはいろいろ試せたので、編集をしていても面白かったですね。
==

『よこがお』(英題:A Girl Missing)
訪問看護師の市子は、その献身的な仕事ぶりで周囲から厚く信頼されていた。なかでも訪問先の大石家の長女・基子には、介護福祉士になるための勉強を見てやっていた。基子が市子に対して、密かに憧れ以上の感情を抱き始めていたとは思いもせず──。ある日、基子の妹・サキが行方不明になる。一週間後、無事保護されるが、逮捕された犯人は意外な人物だった。この事件との関与を疑われた市子は、ねじまげられた真実と予期せぬ裏切りにより、築き上げた生活のすべてが音を立てて崩れてゆく。すべてを失った市子は葛藤の末、自らの運命へ復讐するように、“リサ”となって、ある男の前に現れる。
出演/筒井真理子、市川実日子、池松壮亮、須藤蓮、小川未祐、吹越満
脚本・監督/深田晃司
2019/111分/カラー/日本=フランス/5.1ch/ヨーロピアンビスタ
日本公開/2019年7月26日(金)より角川シネマ有楽町、テアトル新宿他全国公開
配給/KADOKAWA
公式サイト
©2019 YOKOGAO FILM PARTNERS & COMME DES CINEMAS







