【特別対談】『彼女のいない部屋』マチュー・アマルリック監督 × 黒沢清
- Atsuko Tatsuta
※本記事には映画『彼女のいない部屋』のネタバレが含まれます。
フランスを代表する俳優マチュー・アマルリックの最新監督作『彼女のいない部屋』が8月26日(金)より日本公開されました。

物語は、クラリス(ヴィッキー・クリープス)が赤い車に乗って家を出るところから始まります。果たして、夫と息子、娘を残してクラリスはどこへ向かっているのか?ミステリアスな映像と音、バラバラになったピースがやがて繋がる瞬間、ある衝撃的な真実が感動を呼び覚まし──。
フランスの名優として知られるマチュー・アマルリックは、『さすらいの女神たち』(10年)でカンヌ国際映画祭監督賞と国際映画批評家連盟賞をW受賞するなど、監督としても注目されている逸材。第78回カンヌ国際映画祭カンヌプレミア部門でワールドプレミアされた新作『彼女のいない部屋』は、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ファントム・スレッド』やM・ナイト・シャマラン監督の『オールド』などで脚光を浴びたヴィッキー・クリープスを主役に起用した、ある女性とその家族を巡る心の旅。アマルリック監督の最高傑作との評価も得ている野心作です。
日本公開に際して、『ダゲレオタイプの女』(16年)に俳優として出演するなど、親交のある黒沢清監督とアマルリック監督のFan’s Voice独占対談が実現しました。

黒沢清 マチュー・アマルリックさんと最初に出会ったのは随分前のこと。その後も東京やパリなどで何度かお会いしています。スクリーンでいつも拝見し、尊敬しておりますし、心を許して話すことのできる数少ないフランスの映画人の方ですから、こうしてまたお会いできて本当に嬉しいです。
マチュー・アマルリック 確か、最初は2010年にアルノー・デプレシャン監督と来日した時でしたね(※フランス映画祭2010で来日)。そのとき私は『回路』(01年)は観ていましたが、『トウキョウソナタ』(08年)はまだ観ていませんでした。その後、黒沢監督がフランスで『ダゲレオタイプの女』を撮る際に、役者として使っていただきました。一緒にディナーをした際にいただいたグラスは、今もとても大切に使わせていただいています。
黒沢 グラスのことを覚えていただいていたとは、とても光栄です。ありがとうございます。
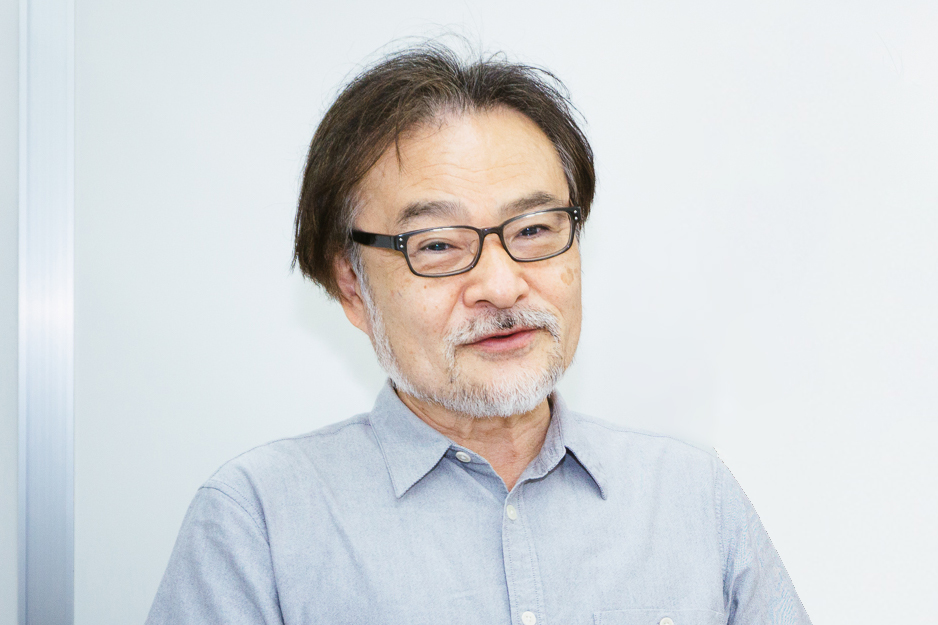
黒沢清監督
では、さっそく本題に入らせていただきますが、本当に素晴らしい映画を観せていただいて、ありがとうございました。前作『バルバラ セーヌの黒いバラ』(17年)にも増して大胆で美しく、複雑で単純で、まさに斬新であると同時に、映画の表現の根源そのものであるかのような作品でした。
物語だけを追っていると、ときに現実と非現実が混乱したりすることもありましたが、映画表現というのは、どれが現実でどれが現実でないかのような境界線をあっさりと超えていくものなんだということが、この映画を観てはっきりしました。ですから僕は、この作品を主人公のクラリス一人の物語だとは思っておりません。それほどまでに、クラリスが冒頭で出て行った後に残された3人──父と娘、息子が現実的で生き生きとしていて、印象的でした。映画の前半まで、クラリスは実は死んでしまった幽霊なのかしらと思っていたほどでした。
それで、マチューさんに質問です。この残された父と娘、息子の印象深さを決定づけているのは、娘の弾いているピアノだと思います。幼い頃も、成長してからも、どちらも鍵盤を叩きつけるような、激しく情熱的で、どこか挑戦的な強烈な弾き方です。ピアノという楽器を選ばれた理由は何だったのでしょうか?それから、俳優にピアノを実際に弾いてもらう撮影はかなり大変だったのではないかと思いますが、その分、本当にその場で弾いている生々しい音が伝わってきました。撮影の苦労なども聞かせていただけますか?

マチュー・アマルリック監督
アマルリック 清さんがおっしゃることに、大変感動しています。まずお答えしたいのは、すべて「あなたの映画を観たから」だということ。私たち人間が頭の中に抱いているような狂気を、人生よりも壮大に映画の中で爆発させることができているのは、黒沢映画ならではです。私たちフランス人は、ともするととても合理主義であったり、デカルト主義的で論理的に説明しようとして映画を矮小化させてしまうことがありますが、あなたは映画の中で、幻想や欠乏感、欲求不満、やりたいけどやれないということを、周囲の空気に漂わせることが出来る監督です。(今作の原作である)クロディーヌ・ガレアの戯曲(「Je reviens de loin」)はとても文学的で、私の中には、黒沢映画の観客としての記憶が無意識に残っているので、まるで考古学者が遺跡を発掘するように、砂の底というか、その言葉の裏に、何かミステリアスなオブジェを見つけようとしました。それが、幽霊や衝動、欲望、あるいは音楽でした。これらが出来たのは、繰り返しになりますが、あなたの映画を観ていたおかげだと思っています。あなたは、映画で宇宙を融合することができます。
なぜピアノなのかと言えば、クロディーヌの戯曲の中にすでに存在したからです。おっしゃるようにピアノがあるからこそ、あの家がより生き生きとしてきます。幼い頃の娘リュシーは、「エリーゼのために」からあまり上達せず、音階練習ばかりしています。クラリスは母親として、娘にもっとピアノが上手くなって欲しく思い、だから、夫と子どもたちを死に追いやったあの古い車のカセットやラジオからはピアノ曲が流れるし、空想の中では娘が成長して、ピアノがすごく上手になっています。でも息子の場合は、彼女の想像のきっかけになるものが見つからず、記憶の中では息子の方が少しずつ印象が薄いのです。

そのピアノの弾き方は確かに独特ですが、あれはまるで木製の棺に釘を打ち込んでいるような、死んでしまったことに対する怒りというものが表現されています。リゲティ・ジェルジュという作曲家の曲のように。そういうピアノの弾き方をするためには、やはり本物のピアニストが必要です。幼い頃のリュシーを演じている アンヌ=ソフィ(・ボーウェン=シャテ)も、成長したリュシーを演じたジュリエット(・バンヴェニスト)も、本物のピアニストです。現場には彼女たちが練習できるように撮影用以外にピアノをもう1台置いていたのですが、彼女たちはコンセルヴァトワール(パリ国立高等音楽院)などの課題のために一生懸命練習していました。ということで、彼女たちが本物のピアニストだから同時録音が可能になり、マジカルと言ってもいい、生き生きとした音になったと思います。
黒沢 なるほど。成長したリュシーが、調律が終わったばかりのグランドピアノを叩くように弾きます。あの曲は何でしょうか?あの激しい曲というか音こそ、どれが現実でどれが空想で、どれがクラリスの希望なのかといったことは関係のない、本当に生々しい映画そのもののような強烈な音だったのですが、あれは音楽だったのですか?

アマルリック そうですね。あそこでリュシーは、本当にピアノが大好きでピアノに恋しているという自分を解放します。ロデオの野生の馬のように突進していく、という感じです。どういう曲にしようか探していた時、アルベルト・ドゥルーといういつもリゲティを弾いていたピアニストのお葬式がありました。その時に流れていたのが、あの曲です。私も知らなかった曲ですが、リゲティの「ムジカ・リチェルカータ 第1番」という曲で、基本的に「ラ」しか弾きません。「ラ」だけずっと、「ラ、ラ、ラ」とだけ。まるでパーカッションのように繰り返し、最後の音だけ「レ」。それを聞いたときに、「これだ!」と思いました。
ジュリエットが演じた成長したリュシーが(アルノルト・)シェーンベルクを弾くシーンも(「6つの小さなピアノ曲 第3番 Op.19」)、学校で習うような行儀の良い、礼儀正しい弾き方ではなく、彼女の中の野性、動物性が炸裂する場面です。難曲中の難曲で、本当に技巧が必要なのですが、やっと成功できたのは、なんと僕のパートナーであるバーバラ・ハンニガン(カナダ人ソプラノ歌手・指揮者)が撮影現場を訪れた時でした。彼女もリゲティと共演したことがあります。

『トウキョウソナタ』の中で、子どもがピアノを弾くシーンがありました。観客に、時に言葉を超えたものを感じさせる、音の響きがありますよね。唸りのような、何かギシギシ軋むような、これは音楽なのかなと思うほどの。音自体が、表現方法として僕たちに迫ってくることがありました。そういう音の使い方を清も私自身もすると思いますが、私はこれからも続けていこうと思っています。
黒沢 なるほど、あれは曲だったのですね、素晴らしいですね。ピアノと並んでこの映画で非常に特徴的に出てくるのが自動車で、僕は自動車に詳しいのですが、あれはAMC・ペーサーという車ですね。ただ、僕は何度もフランスに行っていますが、この車が走っているのは一度も見たことがなく、フランスではものすごく珍しい車だと思います。エンドロールでもペーサーの文字にだけ色がついていたりと、この映画において特別なポジションにあることはわかりますが、なぜAMC・ペーサーを選んだのですか?

アマルリック ストーリーの中でクラリスは車を運転しなければならない設定でしたが、(原作の)戯曲には単に「車」と書いてあるだけで、具体的な車名はありませんでした。撮影が迫ってきて、第1助監督から「どの車を使うんですか?」と聞かれ、ついに私が決めなければならなくなりました。車も役者と同様に、「これを撮りたい」と欲求を掻き立てるものでなければなりませんが、今のモダンな車にはまったく掻き立てられません。でもだからといって、古い車を使う理由も見つかりませんでした。
映画の現場ではたいてい、問題は後回しにされます。難しいことは脇に置いておいて、良いアイディアが降りてくるのを待つ。今回もそうでした。そしてある時、「そうだ、二人(クラリスとマルク)が12年前にディスコで出会った時、マルクがあの車に乗っていたことにしよう」というアイディアが降ってきました。マルクがクラシックカー好きという設定にすれば成立する。その車でマルクと子どもたちが山へ行って遭難するわけで、設定としては悲劇的だけど、その車をクラリスが運転することによって、まるで宇宙船に乗っているように死者とつながる。そういった乗り物になると思いました。
実際に脚本に書き加え始めて、どの車にしようかと助監督や車のディーラーと一緒に考えました。AMC・ペーサーは『ウェインズ・ワールド』(92年)にも出てきます。1977年頃にステーションワゴンが発売されたのですが、V8エンジンなのですごい馬力あり、100キロにつき25リットルくらいガソリンを使うので、燃費が悪い。しかも石油危機の時代でしたから、この車の市場での寿命はとても短く、消えてしまいました。でも、私はとても気に入りました。窓が大きくて、カメラを操作するのが楽ですからね。本来ならフロントにカメラを設置するところを、実際に中に入ってヴィッキーを撮影出来るくらいでした。これは余談ですが、ヴィッキーは本当に車を運転するのが大好きで、素晴らしいドライバーですよ。

黒沢 確かに窓が大きかったですね。宇宙船のようだと言われたら、確かにそう見えました。さらに車に関してお聞きしたいのですが、すごく印象に残っているのは、確かクラリスは海に向かうと言って最初は走り出しますが、その後あの車はどこに向かっているのでしょう?走るシーンが何度もありますが、一体どこに向かって走っているのか、いつも不思議に感じられました。一方で、車が家そのものの続きのようにも見えるし、家とは切り離された、彼女だけの自由なり希望なり孤独といったことの象徴にも見えます。家族たちの場にも見えます。いろいろなものに見えますが、やはり最後も彼女が車で走っていくところで終わりましたね。
アマルリック 彼女は自分の中にパラレルワールドを持っています。人がパラレルワールドを自分の中に持っていることで、人生がもっと豊かになるということがあると思います。空想の世界とも言えるかもしれませんが、映画ではパラレルワールドを表現できます。家というのは、すでに固定してしまった場所ですよね。だからそこでは彼女は暮らせない。彼女は常に人生が自分のものであるために、常に自分を“運動”の中に置いておかなければなりません。そして、もう1回、もう1回という風にやり直すわけです。そのように動いている彼女、つまり車に乗って移動している彼女で最後は終わりたいと思ったわけです。
黒沢 なるほど、面白いですね。確かに動いているんですよ、彼女。どこに向かうかというのはおそらく重要ではなく、動いていることが重要なのですね。まさに映画の中に出てくる車の撮り方として、その解釈の仕方として、他にないくらいの正解だと思います。目的地ではなく、動くことが重要。窓の外に風景が流れ、前を見ている主人公。これほどの映画的な強い表現、気持ち良い表現はないと思いました。

次の質問ですが、この映画は誰が観ても、音と映像と音の編集によって、物語を本当に自由に複雑に構成していくという作り方になっていることがわかります。次に来るカットとの関係における緊張感がここまで洗練され、かつ持続している映画というのは、本当に久しく観なかったなというくらい、非常に強いインパクトを受けました。このことはおそらく多くの人が指摘し、皆が感銘を受けていることだと思いますので、別のことについてお聞きします。
というのは、後半にビックリするようなカットが二つありました。一つは、マルクが勤めている工場で、マルクが奥から歩いてきたら主人公のクラリスが立っていて、その前をマルクが通過し、マルクの上司にあたる中年男性にクラリスが、「マルクはこの後どうなってしまうんでしょう?」と尋ねると、上司が「君が決めて教えてくれ」と言う。それがワンカット。もう一つは、その後に、成長したリュシーが列車でパリへ向かい、もうすぐモンパルナス駅に着くというアナウンスがあり、窓の外にはパリ近郊の景色が流れる中で彼女が立ち上がり歩きだすと、そこは工場の中だったというワンカットがありました。そこはモンタージュに頼らない、現実と非現実、あるいは空想、あるいは社会的な状況、すべてがワンカットの中に入ってしまうという、ビックリするような瞬間でした。驚異的な瞬間ですが、全然モンタージュに頼っていません。こうしたショットを突然紛れ込ませた理由、狙いというものを教えてください。

アマルリック 前提として、この映画の映像を想像しているのはクラリスだということがあります。なので、編集を担当したとても有能なフランソワ・ジェディジエ──黒沢監督もお会いになったこともあるかもしれません──とは、「我々技術スタッフが、裏でマリオネットを操作するようにクラリスを動かすのはやめよう」と言っていました。物語を作るのもクラリス、そしてそれを投影するのもクラリス、編集するのもクラリスということにしようと決めました。
撮影監督のクリストフ・ボーカルヌにも頼み、リアルなショットと想像の世界を同じような美学で撮るように決めました。いわゆるパラレルワールドですが、家に貼ってあるロバート・ベクトルという画家のポスターのように、すべてがハイパーリアリズムなわけです。一見写真のようで、よく見ると絵だとわかる。Tシャツの色まで何から何までを非常に現実的に描いているから、“超”現実(超=ハイパー)。

その二つの映像が出てくるのは、リゲティのダンダンダンと叩くような音楽の後ですね。そこでクラリスは少し我に返るわけです。「想像するのももうこの辺でやめないといけないかもしれない」と。なぜなら、娘と息子がケンカして、娘の日記を燃やしてしまいます。彼女が想像した偽の日記ですがね。すべてがうまくいっていない、間違っているとなり、そして、リゲティの音楽の最後の音符がポーンと鳴った後に、工場が出てきます。不思議なことに、そのアイディアはある朝に思いつきました。あの工場でマルクが歩いてきて、クラリスの前を通る。マルクはクラリスを気に入って、彼女にちょっと笑いかける。でも彼は消えていく。そして、彼女が現実に引き戻されるわけですね。列車のところも同じで、これまでハイパーリアリズムでずっとやってこれた彼女の想像力が立ち行かなくなってきて、想像のフォルムが、あの時点ではみ出してくる。それが狂気とスレスレに近づいてくる。なので、パリのコンセルヴァトワールで娘がオーディションを受けているなんていうシーンも、足元から揺らいでくるわけです。本物の両親が出てきたりしますからね。ということで、清がおっしゃった二つのショットの異様さというのは、彼女がそれまでの割と調和のとれたハイパーリアリズムの想像を逸して、本物の狂気に近づいたからです。
私たちは、パラレルワールドをできるだけ具体的に、ほとんど本物のように描くようにしました。列車の内部で背景がパリの街から工場に変わるところは、編集に頼らない、シンプルなパノラミック撮影です。列車の中から見える風景は後で投影したもので、その工場は、ラ・ロシェルにあるTGVを作っている工場です。

黒沢 なるほど、よくわかりました。おそらく時間的にこれが最後の質問になると思いますが、そういうクラリスの混乱や狂気、あるいは現実と妄想が入り乱れる物語でありながら、彼女の家族以外の周りの人たちがものすごく印象的ですね。カフェのカウンターで隣に座ったおじさんも、フルート奏者だと言う男も。最後の方にも、壁を背に立つ彼女に、おじいさんがイスを出してくれたりします。物語の中心にいない人たちが、彼女に対して実に寛容的で、彼女の錯乱を温かく見守っている感じがして、ものすごくホッとしました。それも彼女の幻想なのかもしれないし、あるいはこれが一つの映画で提示したかった現実というか、こういう混乱する彼女を温かく見守りたいというマチューさんの設定した一つの現実の姿なのかもしれない。どちらかわかりませんが、その周りの人たちがすごく気に入りました。
アマルリック 実はこの作品では、俳優が本職という方は5人しか出ていません。ヴィッキー・クリープスとアリエ・ワルトアルテ、それからガソリンスタンドの女性オーレリア・プティ。彼女は『さすらいの女神たち』(10年)でもガソリンスタンドの女性を演じてくれました。それから不動産屋のエルワン・リバールと、工場の同僚サミュエル・マチュー。ほか、山荘の人も警察の人も素人です。警察の人は、僕らが撮影しようと思っていた家の持ち主です。コーヒーを持ってきてくれる山荘の人も、スペイン人の救助隊も、全部素人です。

撮影中は、ヴィッキーができるだけワンテイクで、多くても2テイクで済むように配慮していました。やはり二人の子どもを亡くすという設定ですし、ヴィッキーも喪失の体験をしていますから、なるべく彼女の負担を少なくしようと配慮しました。でもクラリスは、そうした喪失を抱えたまま仕事もしなければならないし、生きていかなければなりません。人間には、大切な人を亡くした時に限らず、大失恋をした時なども、周りの人たちに助けられて生きていくというところがあると思います。傷ついている人を見ると、なにかと優しくなるものです。自分もひょっとしたら傷ついたり、あるいは狂気に近づいたりするかもしれない、人ごとではなく次は自分の番かもしれないという思いが誰にもあるでしょう。例えば、カウンターで彼女が抱き着く男にしても、それを優しく受け入れます。唯一、ドイツ人の親子には彼女の方が優しくすべきなのに、怪物みたいになってしまいますがね。余談ではありますが、カフェで囁くように喋る男にしても、フルート奏者にしても、本物の役者ではありません。
撮影は春に始めて、幸いなことに遺体が戻ってくるシーンを一番最初に撮り終えていました。死者を追悼するシーンを撮ってから、次は11月、次は1月、雪のシーンという順番で撮っていったのですが、ある時点で、「もうたくさんだ。ヴィッキーは別に聖女じゃないし、虐待されている殉教者でもない。彼女だってもっと笑って、自分の人生を生きたら良いんだ」と、僕も考え直しました。「家族を失ったらどうなるか?そんなことは忘れよう。もっと面白いシーンを作ろう」という気持ちで、車に乗っていったら「いい車ですね!」とナンパされたり、フルート奏者をナンパするシーンを入れました。ということで、フルート奏者のシーンはラストに撮りました。フルート奏者には誰が良いかなとスタッフの中から探して、アリエに胸毛があるので、スタッフの中で胸毛があるジャン・フィリップを起用しました。ジャン・フィリップは子どもが生まれたばかりなのですが、日常ではスーツを着たりせず、すごく人あたりが良く優しくてシャイなので、スタッフの女性たちにも人気です。ということで結論を言うと、狂気に陥りそうな人やすごく苦しんでいる人に対しては、憐憫の情が生まれるものです。なぜならそれは、決して他人事ではなく、自分にも訪れるかもしれない状況だからです。

黒沢 すごく良い話を聞きました。物語上の現実と、物語上の空想と、それから撮影現場というもう一つの現実がそこには映っていたのですね。とても良い雰囲気の撮影現場だったんだろうなと、フルート奏者さんの恥ずかしそうな顔を見て、そう思いました。もっといろいろお喋りしたいのですが、お忙しいところを本当にありがとうございました。
アマルリック いいえ、私の方こそありがとうございました。清には心から感謝しています。本当に感謝、感謝、感謝ばかりです。9月の中旬くらいに日本に行こうと企画しているのですが、その頃は日本にいらっしゃいますか?
黒沢 そうですか、ぜひお会いしたいですね。どこかでうまいことお会いできれば良いですね。
==

『彼女のいない部屋』(原題:Serre moi fort)
家出をした女性の物語、のようだ。
監督/マチュー・アマルリック
出演/ヴィッキー・クリープス、アリエ・ワルトアルテ
2021年/フランス/97分/DCP/カラー/日本語字幕:横井和子/英題:Hold Me Tight
日本公開/2022年8月26日(金)より、Bunkamuraル・シネマ他全国順次公開
配給/ムヴィオラ
公式サイト
© 2021 – LES FILMS DU POISSON – GAUMONT – ARTE FRANCE CINEMA – LUPA FILM







