【単独インタビュー】『流浪の月』李相日監督が“理解されにくい”人々を見つめ続ける理由
- Atsuko Tatsuta
本屋大賞を受賞した凪良ゆうの傑作小説を李相日監督が映画化した『流浪の月』が5月13日(金)より全国ロードショーされています。

雨が降り出した公園で、10歳の家内更紗(白鳥玉季)に傘をさしてくれたのは、19歳の大学生・佐伯文(松坂桃李)。両親と離別以来一緒に住んでいる伯母の家に帰りたくない更紗は、部屋に入れてくれた文のもとで、そのまま2か月を過ごすことに。ところが、ほどなく文は更紗の誘拐罪で逮捕されてしまいます。それから15年後、“傷物にされた被害女児”とその“加害者”という烙印を背負ったまま、更紗(広瀬すず)と文は再会しますが、更紗は恋人・中瀬亮(横浜流星)と同棲中で、文のかたわらにも谷あゆみ(多部未華子)という女性がいました──。
原作は、2020年本屋大賞を受賞した凪良ゆうのベストセラー小説。映画化のオファーが殺到する中、凪良が李監督の映画のファンだったこと、さらには企画書に添えられていた李監督自筆の手紙の内容に共鳴したことにより、李監督による映画化が実現しました。「誘拐犯」「ロリコン」というレッテルを貼られた男と、「被害者」「洗脳された可哀相な人」という好奇の目に晒される女。世間から決して“許されない”ふたりはどのような道を選ぶのか。『悪人』(10年)、『怒り』(16年)など人間という不可解な存在の深淵を探り続ける名匠・李相日が6年ぶりに手掛けた長編は、残酷な世界の中で絆を確かめ合おうともがく男女の切実なヒューマンドラマです。
コロナ禍の苦境を経てついに完成した『流浪の月』公開を前に、李相日監督がインタビューに応じてくれました。

──小説「流浪の月」は本屋大賞を受賞する前に読んでいらしたそうですね。物語の力強さはもちろんですが、映画化する物語としての魅力は何だったのでしょうか?
世の中で言う“常識”と、人の良心の間で生まれる苦痛のようなものが描かれているところでしょうか。このテーマは、『悪人』や『怒り』にも共通する部分もあります。「流浪の月」という小説の文体や表象的な部分は、これまで僕が手掛けてきたものと毛色は違うかも知れませんが、「痛み」という共通の部分に僕の中の針が振れたのだと思います。
──確かに『悪人』や『怒り』と共通する部分もありますが、明らかにこれまでの李監督の作品にはなかった、新しい部分もありますね。
この物語の(主人公である)更紗と文という二人の関係性はものすごく純粋で、見ようによっては寓話のように感じられます。ある種の清廉さのようなものがある二人。「世の中には、こういう関係があるんだろうか?」「あって欲しい」と強く思いました。その寓話的な部分があることで、映像化は難しいだろうと思ったのですが、逆に言うと、寓話的な雰囲気の作品は撮ったことがなかったので、新鮮だとも思いました。大体今までの作品では、月をあんな風に美しく撮ったこともなかったですからね(笑)。
──「こういう関係があるんだろうか?」と思われたということは、現実の社会はもっと残酷なものであると思うわけですね?この物語の中で二人が孤立していく様は、今日の「分断」や「排除」といった問題が顕在化している世の中と密接に結びついていますね。自分と違うもの、理解できないものを排除していく。特にインターネット時代になってその傾向は強まっているようにも思います。二人の親密な関係についての物語ではありますが、そうした社会的なテーマも根底にあることは、強く意識されたのでしょうか?
おっしゃった通りというか、言葉にするとそういうことだと思います。今の時代、人間関係がものすごく短絡化しています。人を排除したり批判したりといったことが、インターネット上で簡単に行われてしまいますよね。おそらく匿名性というか、顔を見なくても出来てしまうからでしょう。だけどそういう人たちも、常にどこか不安でもあると思うんですよ。というのは、いつか自分が“そっち側”の人間になるかもしれない。自分が排除されたり、批判されたりする立場になるかもしれない。そういった不安の裏返しで、排除する側に回ってしまう。紙一重ですよね。
でもだからこそ、この二人のお互いに対する確信性みたいなものが浮き立ってくるのではないかと思います。おそらく、このような世の中だからこそ、(更紗と文のような)こういう関係があって欲しいと、みんなが願うのではないか、と。
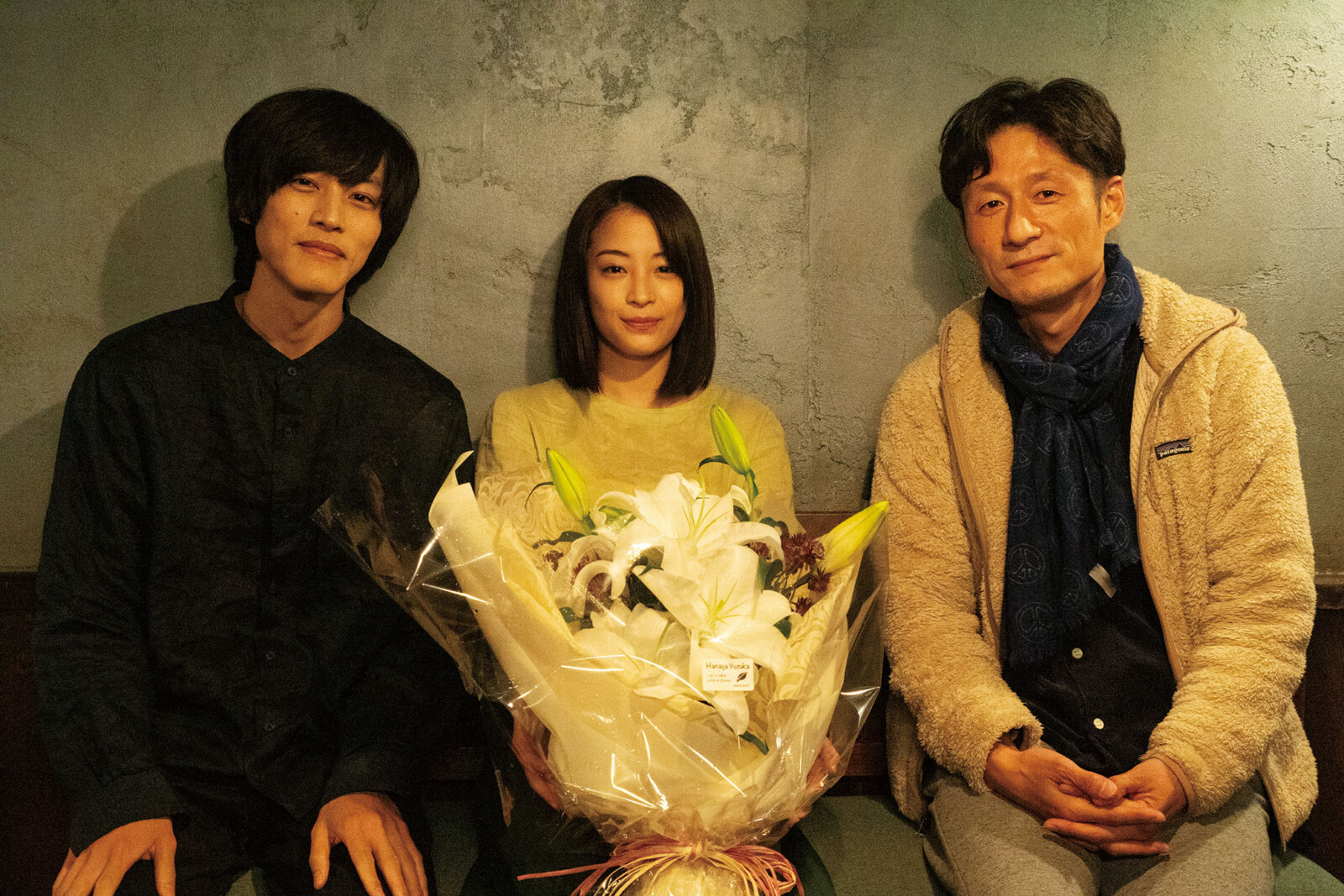
──これまで撮ってこなかった「月」を撮ったということでしたが、自然を大変美しく映し出されていますね。それは意図的だったのですね。
それはホン(・ギョンピョ撮影監督)さんによるところが大きいですよね。この作品の根底には殺伐とした感情があるからこそ、映像的に美しいものが反語として必要です。あまりにも酷い世界を描写するだけでなく、映画を味わっていく上での美しさも必要でした。酷い人間の潜在意識がある一方で、自然は人間とは関係なくこんなに美しく存在しているというのは、両方があってこそ、現実的なのではないかなと思いました。
──初めからそうした画作りのビジョンがあって、ホンさんに撮影監督をお願いしたのですか?
いや、入り口としては違う角度からですね。ホンさんはいろいろな作品を撮影されています。最近だと『パラサイト』(19年/ポン・ジュノ監督)とか『バーニング』(18年/イ・チャンドン監督)などがありますが、どちらかというと今回の映像の手法としては『バーニング』に近いものになっていると思います。『パラサイト』は、ポン・ジュノさんが絵コンテをきちっと描いて、とても緻密に計算された上で撮った映像です。でも今回はもう少し余白が欲しかったというか、『バーニング』に近い手法が良いのではないかと思いました。

李相日監督、ホン・ギョンピョ撮影監督
──ホンさんは、ポン・ジュノさんの紹介だったと伺いました。『パラサイト』の撮影現場に行き、依頼なさったそうですね。
ただただ、ホンさんにやってもらいたい、というだけでした。あれだけの映像を撮られている方なので、何でも良いから一緒に仕事をしてみたかったというのが本音ですが、だからといって何でも良いからオファーするわけにはいきません。『流浪の月』はテイスト的にホンさんが韓国で撮っている作品とは少しトーンが違うので、ホンさんはどう思われるだろうと思っていたのですが、台本の要約を送ったら、受けてくださるとお返事をいただきました。
──ポン・ジュノさんは、李監督の作品にホン・ギョンピョさんが参加することに関して、応援してくださっていたんですね。
最初に僕が、「ホンさんにお願いしたいのですが、どう思いますか?」と聞いたら、「良いんじゃないの。ふたりともちょっと温度感が高いから、合うんじゃないのかな」と言って、すぐにホンさんに繋いでくださいました。
──ポン・ジュノ監督は、李監督のキャラクターをよくご存知なんですね?
ポンさんとは結構長い付き合いです。10年以上前から知り合いだったので、毎作、韓国で上映する際には観ていただいています。大体どういう傾向の作品を作っているのかは理解してくれていると思います。

──同じ“温度感”のホンさんと実際にお仕事をしてみて、いかがでしたか?ホンさんに先日インタビューをしたら、「『パラサイト』の撮影現場でお会いしたときは穏やかで優しい方だったけれど、(『流浪の月』の)撮影現場では厳しかった」というようなことをおっしゃっていました(笑)。
僕もホンさんに対して、同じ印象ですね(笑)。『パラサイト』の撮影現場を訪れた時は、にこやかで柔らかい感じの印象でしたが、現場入るとブルドーザーのようでした。グイグイ現場を引っ張っていくというか、良い映像を撮るということに対しての貪欲さには、ものすごいものがありました。
──ビジュアルに関しては、どのようなビジョンをお伝えして相談されたのですか?
脚本上では室内のシーンが多いのですが、部屋に閉じこもって撮るのではなく、ベランダとか外を感じさせるような撮り方を意識するとか、また、狭い空間で奥行きをどう見せるのかについて、かなりディスカッションしました。室内は、夜にライティングして撮影すると暗く潰れてしまったりするので、室内での夜のシーンも、なるべく昼間に撮ろうということになりました。屋外のシーンは、スカイラインなどは日が暮れる直前の時間を狙おうと話していました。
──室内のシーンが多いからこそ、自然の風景を撮っていこうというアイデアは、ホンさんから出たものですか?
そうですね。

──ホンさんは、日本の自然は美しく、また、韓国より光や空気感が映像的で撮りやすいというようなことをおっしゃっていました。
そうですね。ホンさんは、(ロケが行われた)松本の雲は良いと言っていました。韓国は中国からの黄砂があるせいか、月がこんなに綺麗に見えない、と。なので撮影に入る前から、月は何度かは狙って撮りましょうという話をしていたのですが、実際に撮影して、「こんなに綺麗に月が撮れるんだ」と感動していましたよ。
──『パラサイト』などは建込みでセットを作っていたのでホンさんも構図も決めやすかったと思いますが、『流浪の月』は最初からロケ撮影で行こうと決めていたのですか?特に、大人になった文が経営しているカフェが印象的ですね。(長野県)松本のカフェと聞いていますが、ロケ地として決め手となったのは?
そうですね。特に文のカフェは外との関係性が重要だったので、セットでは考えていませんでしたね。この映画で完全にセットで撮ったのは、亮と更紗のマンション。あの室内だけはセットなんですが、他はロケですね。
文のカフェは、見た瞬間に「ここだな」と、やっと辿り着いた気がしました。良くも悪くも特徴がありすぎない佇まいも良いと思いましたし、あの建物は、外からぽつんと孤立しているようにも見えつつ、通りに面しているので、閉塞感もありません。その通りからは、川や橋も見えて、近くに大きなビルがあるわけでもないので、空が広く抜けています。そういった絶妙な感じが良かった。また、大きい縦長の窓が印象的で、建物の中の空間も気に入りました。ホンさんに「縦長だと撮りづらいですか?」とリモートで相談したら、「『スノーピアサー』ではずっと列車の中を撮影していたから、縦長は良い画が撮れると思う」と言われました。

──この作品は繊細な感情のドラマが核になっていますが、ミステリー的要素もあります。映画としては、ミステリーの要素はどの程度重要視されたのでしょうか。
“言葉の選び方”の違いかもしれませんが、ミステリーというよりは、文の苦悩の根源がどこにあるのかを、更紗の目を通して探し当てるという流れを意識しました。隠している秘密を暴くというよりも、二人の間に何があったのか、あるいはなぜ文がこういう人格なのかというところを丁寧に解いていきたかったし、そこに更紗がどう向き合うのかを描きたく思いました。
──傷つくことを覚悟で、文とまっすぐに向き合おうとする更紗を演じた広瀬すずさんが素晴らしかったです。広瀬さんを更紗役に選んだ理由は?
例えば、松坂桃李君は濁りのない澄んだイメージですけれど、また違った意味で、広瀬すずという人も、存在に嘘がないというか、何か外側に貼り付けているものがない人に、僕からは見えます。自分をこう見せたいとか見せたくないとか、人はいろいろ武装したりしますが、彼女にはあまりそれがありません。かといって、オープンマインドでもないところがとても良いと思いました。

──松坂さんと広瀬さんは、どちらを先にキャスティングされたのですか?
すずが先ですね。とはいえ、すずに合わせて桃李君を選んだというわけでもありません。文を誰にするか考えた時に、桃李君以外は考えられず、実際にお会いする前に決めました。言葉でその理由を言えると楽なのですが、直感ですね。僕の目から見ると、そう感じるという。それが外れているかもしれないけれど。
──直感に頼るタイプですか?
直感しかないですね(笑)。
──この時期に撮影された作品はコロナ禍の影響を受け、みなさん苦労されていますが、『流浪の月』の撮影で大変だったことはなんでしょうか?
脚本も大変でしたし、現場もコロナの影響があって大変でしたし、確かにホンさんとの毎日のディスカッションも大変でした(笑)。まず、ホンさんが合流するのが遅れました。隔離期間が終わって顔を合わせたのが、撮影開始前、10日を切っていましたから。尋常じゃない短さでした。しかもお互い初めてだし、絵コンテも無い中で、その場で俳優の動きや場所の状況、光の具合を見ながら、画を決めていくのが大変でした。とにかく、そのシーンのワンカット目をどうするのかを決めるのに時間がかかりました。このシーンは何を最初に映すべきなのかを、時間をかけて話し合いました。

──日本人の撮影監督と仕事する場合と決定的に違うことはありましたか?
日本人か外国人かというより、ホンさんだから、という気はしますが、とにかくホンさんにとってはフィーリングが大事なんです。いろいろ話し合って決めたカットをカメラで切り取っていった時に、この画からはちゃんと何か生まれているか、「キターッ」という感触があるかどうかが重要です。というより、それがすべて。「キターッ」となったら、やっと次のカットに移ります。もちろん演技的にOKかどうかというのも関係しますが、その判断基準はホンさんならではですかね。
──その「キターッ」というのを待つことに慣れるまでに、時間がかかったのですか?
いや、僕が「キターッ」と思っていると、ホンさんも思っているので。ホンさんとしては“来て”いても、演技的に僕がもうちょっと続けてみたいという時は、なかなか説明は難しいですがね。
──ビジュアルの感性の相性はとても良かったのですね。また是非組みたいですか?
もちろん。感性が合ったと僕が言うのはおこがましいですが、ぜひまたお仕事をしたいですね。

──李監督の作品からは、「理解されないもの」「理解されにくいもの」を突き詰めて、その深淵を覗き込むような感覚を得るのですが、そういったテーマに興味をもつ理由は?
たぶん、人が生きていて苦しむ点は、そこなのではないかと僕が思っているからですかね。例えばSNSにしても、あれだけ“いいね”を欲しがるとはどういうことなのか。“いいね”がないと不安でしょうがないという感覚とは、何なのか。人に承認されたい、認められたい、理解されたい、誤解されることを恐れる──そうしたことから、人はなかなか逃れられないですね。本来、そういうものから自由になるためにネットやメディアがあるはずなのに、現実は逆。不思議だし、おかしいし、理不尽。でも、“いいね”を欲しがりながらも、どこかで僕と同じようにおかしいと思っている人もいるし、嫌だなと思っている人もいると思います。そのままならない感じが、ずっと僕について回っています。
──そこに興味がある?
興味があるというより、「近くにある」という感じがしますね。たぶん、声高に批判しようとか、変えていこうという訳ではないのですが、この気持ち悪さはみんなが一方で共有していることなのではないかと思います。
==

『流浪の月』
原作/凪良ゆう「流浪の月」(東京創元社刊)
出演/広瀬すず、松坂桃李、横浜流星、多部未華子 ほか
監督・脚本/李相日
撮影監督/ホン・ギョンピョ
製作総指揮/宇野康秀
製作幹事/UNO-FILMS(製作第一弾)
共同製作/ギャガ、UNITED PRODUCTIONS
日本公開/2022年5月13日(金)全国ロードショー
配給/ギャガ
©2022「流浪の月」製作委員会







