【レビュー】『Arc アーク』における“死”の科学と“SFらしさ”
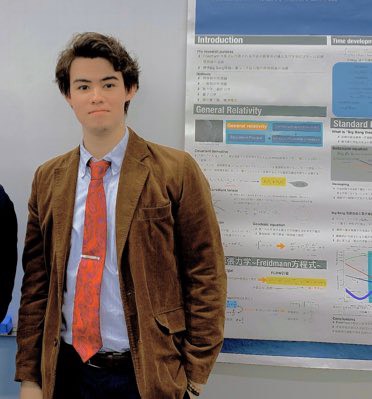
- Joshua
人は死ぬ。それは紛れもない事実である。現在に至るまで、全ての生命にとってのある種の終着点である「死」という状態は、人間精神に多大なる影響を及ぼしてきた。日頃私たちが「死」を直接的に意識することは殆どないが、それでも「生」を強調するため、「死」を引用することが多々ある。「人は死ぬからこそ、今を必死で生きられる」「人生は一回だからこそ、チャレンジしなきゃ」といった文言をしばしば耳にするだろう。「死」という状態は、その回避不可能性が絶対的な象徴としての「死」を形作り、まるで頑強な金属が私たちを取り囲むかのように「生」を浮き彫りにする。私たちは「死」自体が何であるかが本質的に分からないために、その奥にある世界を想像し、神格化してきた。「死」によって形作られる「生」であるところの私たち人間は、死ぬからこそ生きていられるのである。
しかし、死という状態は細胞で構成された生物に確認される現象である以上、歴然とした科学的プロセスであることは間違いない。ペニシリンに始まる抗生物質の開発は、間違いなく人類と死の距離を押し広げてくれた。科学文明のこうした恩恵の極限に、死を克服した人類を想像するのは自然なことと言えるのではないだろうか。

『Arc アーク』はプラスティネーションを応用したストップエイジング技術によって不老不死が実現した世界で、死の克服という恩恵を授かることになった最初の人間・リナ(芳根京子)の”一生”を描いた物語である。本作は中国系アメリカ人SF作家のケン・リュウの「円弧(アーク)」が原作となっている。私が同氏にインタビューを行った際にも彼は言及していたが、どうやらこの「永遠の命」というテーマは彼のインスピレーションをよく刺激するらしい。実際、彼は「円弧」と同じ宇宙(世界線)を共有している可能性もあるとする「波」という作品も書いている。「円弧(アーク)」が地球上で展開する物語なのに対し、「波」の舞台は“地球上で不老不死の技術が確立した”と伝えられた宇宙船である。通底するテーマは同じものだが、「波」は「円弧」の時間的にさらなる先も含めて書かれた物語であり、「永遠の命」を与えるテクノロジーが予期する2、3段階先の未来が想像されている。逆に「円弧」は、“永遠の命”を手にした世界初の人間の精神という内的宇宙を描くことにより深く集中した作品だといえよう。
「円弧」はリナという個人によりフォーカスしたミクロ的な側面をもつ物語であったからこそ、リナの精神世界という宇宙が──“永遠の命”への認識が徐々にアップデートされていく科学文明との相互作用により──変化していく様を鮮明に描くことができていた。リナという1人の人間の一生を見て、私たちは自身の死生観を問い正すことになるかもしれない。あるいは、ますます「死」の存在が人間には必要不可欠なものと再認識するかもしれない。いずれにせよ、私たちが日常常識だと信じていたことが、テクノロジーによる変革により突如そうではなくなったとき、ある人間の持つアイデンティティーや世界認識がどう変わるのか?という問いに端を発した作品が「円弧」であり、『Arc アーク』である。
これをSFと呼ばずして、なんと呼ぶのだろうか?

ここからは、『Arc アーク』を劇場でご覧になった方々に向けて、そもそも科学的に生物が死ぬとはどういうことなのか、なぜ死ぬ必要があるのかを語る場にしたいと思っている。私の文章に見え隠れする思想はどちらかと言うと、『Arc アーク』の天音(岡田将生)に近いものだろうと思っている。石川慶監督と対談し、私がプラスティネーション技術などに対する私見を述べた際、「同じ内容のことを天音に喋らせる予定だった。時間制約のためにカットしたが」と仰っていた。なので、私改め天音視点で、『Arc アーク』のレビューをしていきたいと思う。
死とはいかなるプロセスか
さて、話の腰を折るようで申し訳ないが、死というプロセスは、科学的に完全にその機構が解明されているわけではない。未だ謎も多く、不老不死技術を確立させるために突破しなければならない壁もいくつかある。それでも、ある程度は分かってきた、というのも事実だ。近年、分子生物学の発展は、科学の他分野とは比較にならないほど急激な発展をなぞってきた。
通称多細胞生物と呼ばれる人体を構成するのは、60兆個の細胞である。その死とはつまるところ、その構成単位である細胞の死に繋がっているはずだろう。実は人間の死因にいくつかの種類があるように、細胞にもその死因で区別される死が存在する。ネクローシスとアポトーシスがそれだ。
細胞は有機物で構成されている以上(物質で構成されている以上と言っても良いが)、一定以上の強いエネルギーがぶつけられると、構成分子が破壊され、修復不可能な状態となってしまう。日焼けした肌というのは、その部分の細胞が太陽光からの強いエネルギーを持った紫外線に”破壊”の一歩手前まで侵入を許した結果であり、さらにそのエネルギーを増せば細胞は黒焦げの状態になってしまうだろう。このような外的要因による細胞死をネクローシスという。人間の死に喩えるなら、事故死に相当する。
反対にアポトーシスは、自殺に相当する。細胞が自発的に判断して自身の死を決断するのだ。例えば人間は、母親の子宮内では実はエラや尻尾のようなものを持っていたことをご存知だろうか。当然、今の私たちの身体にはそんなもの付いていないが、一体どこに消えたというのだろう。答えは簡単である。その部分は自殺して、とうの昔にいなくなったのである。人間に限らず、哺乳類や両生類などといった多細胞生物は、その成長の過程で必要な部分はそのまま残り、必要ではない部分は、DNAレベルで予めプログラミングされていた設計図の要請に従い自死していく。こうして徐々に「必要な部分」だけが残った形態が構成されていくことになるのだ。人間の手も最初から5本指の構成を目指して形態変化していくのではなく、最初はあんぱんのような丸い一様な手から始まり、輪郭を浮かび上がらせるように、徐々に不必要な部分がその生を離脱していく。このような細胞の自殺的プロセスは、「プログラミングされた死」と呼ばれている。

さて、ここで人間の死についてもう一度考えてみよう。よく考えてみると、私たちは日頃絶えず飲食を通してエネルギー補給を行っている。エネルギー保存則を考えれば、当然受け取ったエネルギー以上のエネルギーを外に出すことはできないが、少なくとも食事でいつもエネルギーを補給できているわけだから、それが途切れない限り永遠に動ける肉体であっても、物理法則には違反しないのではないだろうか。しかし言わずもがな、人間は死ぬ。私たちがエネルギーを身体に投与し続けても、身体は死に向かっていくだろう。なぜか。
一見矛盾している身体の死に向かうこの慣性は、物理学的な観点からだけでは当然説明がつかない。前述の通り、死のプロセスは完全に解明されているわけではないが、少なくともアポトーシスが関わっていることは明白だろう。人間の形態変化に利用されていたアポトーシスは、私たちが”いずれきちんと死ぬように”、あらかじめその運命を定める役割も担っているのである。
そのような運命は一体どのように定まっているかというと、細胞の染色体の末端構造がそれを決めている。いわゆる、テロメアと呼ばれている部分だ(正確には「テロメアDNA」)。このテロメアはヒトの場合、TTAGGGという塩基配列を持ち、この配列を単位として以降反復的に続く。一回細胞分裂するごとにテロメアは短縮していき、およそ50回〜70回程度分裂したところで、細胞は老化状態と判断され、次第にアポトーシスを行なっていく。細胞がある一定の役割を終えたところで、死が宣告されて華麗に生の現場を退場していくことで、細胞がガン化されることを防ぐ役割もある。要するにテロメアは”命の回数券”なのである。
『Arc アーク』でリナが不老不死の施術を受ける際に注入されていたピンクの液体は、「テロメア初期化細胞」と呼ばれている。そう、”命の回数券”を絶えず初期化することでアポトーシスが起こることを防ぎ、身体全体の老化プロセスを回避することができるのだろう。アポトーシスを不活性化させることは重篤なガンの発生確率を高める可能性があるが、「テロメア初期化細胞」と一緒にナノサイズのコンピュータが注入されていると、原作の「円弧」には書かれている。微細なコンピュータが肉体をくまなくモニタリングし、人体にとって有害な細胞が発生しないように徘徊して回るのだろう。

なぜ人は死ぬのか
ここで「死」についての考察に一度戻ろう。そもそもなぜ、命あるものは必ず死ななければならないのだろうか。実はそうではない。少し時間の針を戻そう。約40億年前、地球に生命と呼べるモノが誕生していくが、当然最初から哺乳類のような複雑な生物が出来上がるわけはなく、最初は非常に単純な(それでも化学的には複雑な)単細胞生物からスタートした。大腸菌は聞き馴染みのある単細胞生物の1つかもしれない。人類が地球に誕生する遥か前から、大腸菌はこの世界の住人であったわけだが、実は大腸菌は「死」というプロセスをそもそも持ち合わせていない。正確に言うと、事故死的な意味のネクローシスが起こる可能性はもちろんあるが、決められた細胞分裂の回数上限を超えると自死するようなメカニズム、つまりアポトーシスを大腸菌は行わないのである。大腸菌に「老化」という概念は無いのだ。
このことは生物が単細胞生物から多細胞生物へと進化していく中で、なんらかの生物学的利益が見出されたために、アポトーシスという過程、もっと広義的に言えば「老化」、そしてそれに続く「死」という過程が獲得されたことを意味する。一体いかなる利点があったというのだろうか。その答えは「環境変化に対応する多様性」にある。なんだ、よく聞く話じゃないか、と思われたかもしれない。実はそこまで単純な話ではなく、ここでいう「環境変化」とは「地球環境の変化」を意味しない。別の対象に対する「多様性」の獲得が、生物はどうしても必要だったのだ。

メイキング写真より
地球環境は時間が経てば確かに変化していき、生物もそれに対応するために進化する必要があるが、かといってそれが「死」を獲得するための最もな条件にはならない。それは大腸菌が行うような無性生殖が、相手が居なくても勝手に分裂して増殖可能であることに由来する。繁栄という目的からすれば、無性生殖の方が遥かにスピーディーに増殖できるわけで、私たち人間がわざわざ繁殖性能の劣る有性生殖を選んでいるのは不思議である。しかし有性生殖は異なる個体同士(オスとメス)の染色体を混ぜ、新たな個体を生成することができるため、「多様性」を確保することができる。そしてその「多様性」を維持するためにも、用済みの親個体は徐々に老化していき、その数が減っていく。このようにして種全体の形質が世代間で更新されていく。が、地球環境を急激に変化させるシミュレーションを行ったところ、この有性生殖による「多様性」の恩恵は、無性生殖による高度な繁殖性能の恩恵を数学的に上回ることが出来ないことが、1978年の時点で示された。つまり地球環境の変化程度のゆるやかな変化は人間にとってさほど驚異とならず、わざわざ「死」を獲得する必要がなかったほどのものだったということだ。
では一体何に対応する必要があったのか。答えを言ってしまうと、それは「ウイルス」である。そう、ウイルスは非常に短い期間で変異し、人類に対する攻撃パターンを直ぐに変えてくる。多細胞生物にとって、そして人類にとって問題となった急速に変化する「環境」とは、地球規模の気象現象ではなく、一世代という短いスパンでの素早い対処が要求される”多様性”を持ったウイルスだったのである。コロナウイルスの変異株の出現が昨今世界を騒がせているのも同じことであり、現在に至ってもウイルスと人間のイタチごっこが継続しているのは、我々の進化形式からして運命づけられたことだと言えるだろう。

『Arc アーク』のSFらしさ
さてそうなると、『Arc アーク』で描かれたプラスティネーションを応用した不老不死技術は、実は興味深い時間的作用を持つと解釈できる。生物が進化の過程でウイルスに対抗する多様性実現のために「死」を獲得したのならば、「永遠の命」を約束するプラスティネーション技術は人類を「死」の無かった大腸菌時代に巻き戻すことを意味しており、これは時間的には進化の道筋を逆流する行為に等しい。私は別にこれが退化だと言いたいわけではない。自然選択の結果として獲得された「死」が、高度に発展した科学文明によってそれがやはり不必要だと判断され、そのプロセスが除外されるというのは、ある意味で自然と人間を分離させる行為に他ならない。今まで生物学的な進化に”進化”を任せてきた人類は、ついに次のステップを踏み出す動力を科学文明に明け渡したのである。
『Arc アーク』と「円弧」の非常にユニークな点は実はここにある。不老不死技術は一見して、自然の客体化を推し進め、ひいては人間の身体性の精神からの分離を加速させるものである。SF的文脈でいえば、サイバーパンクの機械的・生物工学的ギミックがそれだろう。サイバーパンクで提供される身体性は、例えば不老不死を達成する技術ならば、まず間違いなく生体を機械化する方向に向かわせるものであるはずだ。そして大抵の場合、機械化されたポスト・ヒューマンは、置換された身体にではなく抽象的な精神そのものに、そのアイデンティティを見出そうとすることが多い。
しかし『Arc アーク』で映像化された「永遠の命」に繋がるプラスティネーションをはじめとした技術はどうだろうか。ケン・リュウはシルクパンク(※)という造語を使っていたが、『Arc アーク』で見られた科学技術は全て有機的なものであった。「永遠の命」を手に入れた後も、リナの身体は施術前の身体と外見ではまるで違わず、リナは文字通り「永遠の若さ」を獲得していた。『Arc アーク』では冒頭からダンスやボディワークスの作品を通じてその身体性が絶えず強調されていたが、有機的外見による永続的な身体の達成は、ある意味サイバーパンク的技術のものよりリアリティのあるものと感じられた人も多いかもしれない。それがこの『Arc アーク』という作品の良い意味で怖く感じられる部分なのだが、ともかくも、不老不死技術という進化の逆を行くようなテクノロジーと、「永遠の若さ」を保つ自然と調和した有機的なベールに包まれた身体という元来バランスの欠けた二つの概念が、一つの画に収まっている芸術を目の当たりにすることができるのが『Arc アーク』という作品のSFらしさであり、稀有な点なのである。

ここまでで私が何度も「SF的」とか「SFらしさ」という言葉を使っているのは、なぜか。『Arc アーク』のような人間の精神を深く描いたSF作品が世に出ると、「これはもはやSFではなく、ヒューマンドラマだ」という言葉が褒め言葉になる現象が散見されるようになるからだ。ケン・リュウ自身も作品をジャンル分けされるのは嫌っているようなのでそれはそれで良いのだが、しかしやはり、SFの可能性は無限大であると言わせてもらいたい。日頃当たり前だと思っていた常識が、テクノロジーによってある日突然瓦解したとき、人間の世界認識の変貌を描くのが私にとってのSFである。科学それ自体は人間の好奇心から出発した学問であるとはいえ、その客観性の保証のために、人の内観的態度は学問の中身から積極的に削ぎ落とされてきた。私にとってSFとは、そこに物語のスパイスをふりかけ、人間の精神を文学の梯子を借りて再度壇上に上げるプロセスのことを指す。その中で、『Arc アーク』という非常に内的で、ミクロ的でありながらも壮大であるという両義的な意味を持つ物語のSFが日本で制作されたことに、SF好きの1人として私は心から感謝したいのだ。
そして最近、中国系SFとして世界を圧巻しているのが「三体」なのだが、あれを映像化しようと思うととんでもない予算が必要なことは明白だ。だが、「三体」の映像化は既に進行中であることは訊いている。「三体」はいわゆる宇宙SFで、改革開放以後に急激に形成された中国のSF文化が、科学の花形であるところの”宇宙”を題材にした作品で海外を席巻しているのは、いささか象徴的である。映像技術の進化に伴って、これまで映像化不可能であった小説作品を映像化しようという流れが否応なく発生しているのは仕方のないことだと思うが、私は「円弧」そして『Arc アーク』という原作と映像作品の2つの関係性は、SFとして極めて美しいものなのだということを強調したいばかりである。

※ シルクパンク
SFのジャンルの1つにサイバーパンクがあるが、典型的なサイバーパンクには人体を様々なモジュールを用いて生物工学的に拡張し、高度に発達した未来社会の”ネットワーク”に身体レベルで接続可能になった人類(ポスト・ヒューマン)が登場する。サイバーパンクは主に80年代に成立し流行したジャンルだが後に派生し、スチームパンクというジャンルを生んだ。スチームパンクはサイバーパンクと同様に高度に発展した未来社会を描きながらも、登場するギミックの大部分は発達した蒸気機関として描かれる。そしてケン・リュウによれば、シルクパンクとは、結局現実には達成されることのなかったテクノロジーに対する思いが具現化した世界観であるという点ではスチームパンクと同様でありながら、絹や竹などといった東洋アジアで重要視された素材、そして鯨の骨や魚の鱗など海洋文化によるものなど、有機的な素材に重点を置いたジャンルのことだ。
==

『Arc アーク』
舞台はそう遠くない未来。17歳で人生に自由を求め、生まれたばかりの息子と別れて放浪生活を送っていたリナは、19歳で師となるエマと出会い、彼女の下で<ボディワークス>を作るという仕事に就く。それは最愛の存在を亡くした人々のために、遺体を生きていた姿のまま保存できるように施術(プラスティネーション)する仕事であった。エマの弟・天音はこの技術を発展させ、遂にストップエイジングによる「不老不死」を完成させる。リナはその施術を受けた世界初の女性となり、30歳の身体のまま永遠の人生を生きていくことになるが…。
原作/ケン・リュウ「円弧(アーク)」(ハヤカワ文庫刊 「もののあはれ─ケン・リュウ短編傑作集2」より)
脚本/石川慶、澤井香織
音楽/世武裕子
監督・編集/石川慶
出演/芳根京子、寺島しのぶ、岡田将生、清水くるみ、井之脇海、中川翼、中村ゆり、倍賞千恵子、風吹ジュン、小林薫
製作/映画『Arc』製作委員会
製作プロダクション/バンダイナムコアーツ
2021年/日本/127分/スコープサイズ/5.1ch
日本公開/2021年6月25日(金)全国ロードショー!
配給/ワーナー・ブラザース映画
公式サイト
©2021映画『Arc』製作委員会







