【単独インタビュー】『MISS ミス・フランスになりたい!』主演アレクサンドル・ヴェテール
- Atsuko Tatsuta
フランスでモデルとして活躍しているアレクサンドル・ヴェテールの初主演作『MISS ミス・フランスになりたい!』は、男性であることを隠してミスコンに挑戦する青年の成長を描いたヒューマンドラマです。

9歳の頃、学校で将来の夢について「ミス・フランスになりたい!」と発表し、クラスメイトから冷やかされた経験から、その夢を封印したアレックス。その後、両親を失ったトラウマから自分自身のあるべき姿を見い出せなくなった彼は、25歳になり、旧友と再会したことをきっかけに、眠っていた夢を掘り起こし、男性であることを隠して「ミス・フランス」コンテストに挑戦する──。
俳優や脚本家としても活躍するルーベン・アウヴェスが、インスタグラムで見つけたヴェテールに触発され、原案・脚本を練り上げたというストーリーには、実際にヴェテールの生き様が反映されています。日本公開に際し、本作で第46回セザール賞で新人男優賞にノミネートされたばかりのアレクサンドル・ヴェテールにオンラインでインタビューしました。
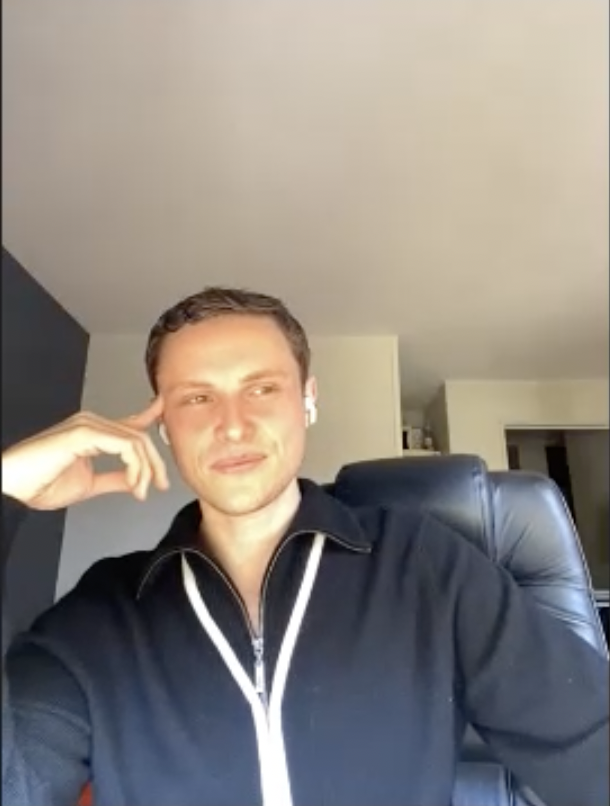
──セザール賞新人男優賞にノミネートされましたね。おめでとうございます!
ありがとうございます。3月12日のセレモニーも楽しみにしています。
──どんな衣装を着用するのですか?
(笑)まだ決めていません。でも、受賞したら壇上で口紅を塗ろうかな(笑)。
──『MISS ミス・フランスになりたい!』は、監督がインスタグラムを通じてあなたに連絡したことがきっかけだそうですね。
テレビドラマのためにインスタグラムを通じて連絡をもらったのが最初でした。正直、彼が誰なのか知りませんでした。最初のインタビューの後、彼の監督作『La cage dorée』(13年)を観てとても感動したので、彼に電話して、長編映画をつくるべきだと提案しました。そうやってこの冒険は始まりました。
──脚本を読んだ時の感想はどんなものでしたか?
アイデンティティというテーマに、新たな視点で問題を提起することができると思いました。今日の社会で男性はどのように自分の中の「女性らしさ」を受け入れるのか、自分の「男性らしさ」が他の人と違っていた場合、どのように自分の居場所を見つけるのかについて語られていました。これはとても現代的なテーマです。豊かな人物描写によって、私が好ましく思う女性たちが描かれていたことも嬉しかったですね。
──完成した作品を観た感想は?この作品はあなたに何をもたらしましたか?
とても感動しました。100%好きな作品ですね。この作品に魂を込めましたが、監督のルーベンと彼のスタッフは、私の魂を素晴らしい形でスクリーンに映し出してくれたと思います。もちろん、初めての主演作となった本作は私に多くのものをもたらしてくれました。私が抱える問題への答えさえ、くれたような気がします。この映画に出る前と出た後では、自分は同じ人間ではありません。主人公アレックスは、映画の最後には成長しますが、私自身も成長したように思います。自分の実人生とこのアレックスの人生の間には、こだまのように対応する部分がいくつもあります。仕事としてだけでなく、この映画での経験は、私に多くのものを与えてくれました。俳優であることが、人生の一部であると自覚しています。

──最初はモデルとしてキャリアに花咲いたわけですが、役者もやろうと思ったきっかけは?
昔から俳優になりたいと思っていました。でも、それを自分で責任をもって引き受けてこなかったんです。でも、ジャン=ポール・ゴルチエのショーに出るという夢は実現することができました。難しいことだと思っていたのに、実現できた。時間はかかりましたけれど。その時、別の夢を見ても良いんだと思いました。だから、はっきりと俳優を目指し始めたのは、2015年にゴルチエのショーに出た時といえますね。ゴルチエのショーに出た後、エージェントから『ヴェルサイユ』というTVシリーズでエキストラの話が来ました。その撮影現場で偉大な俳優たちの立ち居振る舞いを見て、新しい世界を発見し、俳優になりたいと思いました。
──憧れの俳優や監督はいたのですか?
ペドロ・アルモドバルが昔からとても好きでした。幻想的な冒険譚も好きなので、10代の頃は『ハリー・ポッター』シリーズや『インディ・ジョーンズ』、『スター・ウォーズ』のようなまったく別世界で展開される大作もよく観たけれど、具体的にどれか言われれば、アルモドバルの『ハイヒール』(91年)でしょうか。スペイン的な、熱く情熱的なところにいつも触発されます。

──ゴルチエのショーには、どのような経緯で出演することになったのですか?
ちょっと長くなるのですが……高校卒業後、芸術を学ぶために南フランスのヴァール県の小さな街からパリに出てきました。憧れていたゴルチエのショーに出たいと思い、ブティックの前で出待ちをしていました。自分の写真とプロフィールを入れたブックを持って待っていましたが、全然彼と出くわさない。そこで、何週間か経ったある日、受付に行って、長い間出待ちをしているのだけれど彼に会えないと言ったら、彼女は、”何日も前からそこにいたのは知っている。何をしているのかと思っていた”と言って、ゴルチエのショーのキャスティングディレクターの電話番号をポストイットに書いてくれました。それで彼に電話して、写真と履歴書も送ったのですが、ショーへの出演依頼はありませんでした。けれど、3〜4年後にそのキャスティング・ディレクターから電話がかかってきて、出演を依頼されました。それはデヴィッド・ボウイが亡くなった翌日で、今でもはっきりと覚えています。夢は実現できるのだと確信しました。時間はかかったけれど、その過程が面白いのです。だから、自分は今からでも俳優になる夢を追ってもいいと思い始めました。
──キャスティングディレクターに渡した写真では、どんな服を着ていたのですか?
男性の服を着ているものと、女性のドレスを着ているもの両方を渡しました。
──キャスティングの決め手について、ゴルチエは話してくれましたか?
いいえ、聞いていません。いずれにせよ、モデルとして働き始めてから、ジャーナリストとかメイクアップアーティストとか知り合った人には、自分の夢はジャン=ポール・ゴルチエのショーに出ることだと言い続けてきました。だから、彼の耳にもその声が届き、私がしていることを見てくれていたのかもしれません。

──故郷にいたときには目立ちたくなかったので、女装は祭りの時などでしかしなかったと他のインタビューで読みました。女性用のドレスを着たりメイクをしたりするのが自分の表現方法だと、どのように自覚したのですか?
造形美術の勉強をするために、故郷の街を離れた時からですね。芸術の世界こそが、自分自身であり得る寛容な世界だと気がついたからです。パリで芸術の世界に入ることによって、自分が安全だと思うようになりました。自身についてを自由に話せて、100%生きることができる。自分の中にある女性性を発展させたからといって、批判されることはありませんでした。そのおかげで、モデルにならないかというオファーが来ました。人生を一種のパフォーマンスとして生きることができるようになったんです。
──ジェンダー表現についての議論は日本でも活発になってきています。あなたは、女性の服を着たりメイクをすることから、ジェンダーレスモデルとかジェンダーニュートラルなどと呼ばれることがありますが、そうした呼び方は適切なのでしょうか。
なんと言っていいかわからないのですが、カテゴライズすることは好きでないので、自分ではそういう肩書は名乗りません。自分自身であることが大切であると思うので。自分というカテゴリーの中にいるとしか言えませんね。自分に求められること、自分がやりたいことをやっていくだけです。表現できるのは、自分だけです。自分の中にある曖昧さ、自分の中にある女性性を含めて、自分でしか表現できないものがある。ジェンダーニュートラルとか、そういうカテゴリーに自分を入れてしまうと、自分を制限することになってしまいます。”自分自身であること”だけであれば制限もありませんし、”自分は何である”という定義は、どうでもいいことのように思えます。自分らしくあることだけが、重要なのです。
それに、”ただ自分らしくある”ということだけでも、とてつもない努力が必要です。もっと言えば、的を得た言葉がない。自分自身、男性として生まれたけれど、自分の中にある女性性と調和して生きています。それくらいのこと。とてもシンプルな言い方になってしまいますが、シンプルなのは良いことですよね。アレクサンドルという名前の語源は、ギリシャ語で”守る人”という意味です。人類を守る人。それで十分に私のアイデンティティになっていると思います。

──スティーブン・ダルドリー監督の『リトル・ダンサー』などでも、ボクシングは男性らしさの象徴として登場します。この映画の中でアレックスはボクシングジムで働いていますが、その意図についてアウヴェス監督と話しましたか?
はい。ルーベンは、“アレックスはジムで自分が何をしているのかよくわかっていないんだ”と説明してくれました。ボクシングは男性の世界であって、それはアレックスには理解ができない世界です。でもそこに近づいて、観察し、学ぼうとしている。男性的とはどういうものかを、理解したいと思っている。なぜなら、男性にならなければいけないと思っているから。
それから、ボクシングは自分との戦いでもありますよね。アレックスの戦いはミス・フランスになることですが、その対比が面白いと私は思いました。それに、男性の世界であるボクシングのチャンピオンのエリアスは、アレックスのことを理解し、サポートしてくれる友人であるということも面白いですね。一方で、ボクシングはある種の死を象徴する競技です。お気づきになったかもしれませんが、ボクシングジムの窓からは墓場が見え、そこには、アレックスの両親のお墓があります。彼がボクシングジムで働いている理由のひとつでもあります。
──映画中、アレックスは男性であることを偽り、女性たちに混じって過酷な訓練を受けるわけですが、演じていていかがでしたか?
楽しかったけれど、大変でした。まるで耐久レースのように。2ヶ月間、アレックスと同じように、ミス・フランスの最終選考会に出場するために訓練したのですが、ヒールの靴や衣装に耐えるだけも大変でした。本当に大きなチャレンジで、これこそ自分自身との戦いでした。でも、素晴らしい体験だったので、もう一度やれといわれたらもちろんやりますよ!

──今日ではルッキズムに対する批判も高まっていますが、あなたは自身の”美しさ”について、どのように感じていますか?
自分のことを美しいと思ったことは一度もありませんし、どう言葉にしたらいいかわかりませんが……偶然モデルになりましたが、何をするにしても、自分の体験を通してアイデンティティを深めていくというアプローチをしているようなものなのです。自分で考え抜いてアプローチしているので、しっかりとした基盤があります。なので、もしそれが他人に気に入られなくても、また美しいと思われなくても、それはどうでもいいことなんです。確かに、生まれもった顔やルックスはありますが、それを使っているのは“自分”なのです。オリジナリティがなければ、誰の興味も惹かないでしょう。私が興味を持っているのは、いわゆる男性的な美しさではありません。けれども、それを自分のものにしたことによって、私の力になりました。
──あなたも主人公アレックスのように、「他と違うこと」で葛藤したり、偏見にさらされたことはありましたか?
ありますよ。でも、そうしたステレオタイプ的な価値観の犠牲者にはなりませんでしたし、それに対する戦いも止めていません。多少問題が生じても、深いところにある自我が傷ついたことは一度もありません。私という人間を揺るがすまでには至らないのです。

──ここ最近、シスジェンダーの女優がトランスジェンダーの役を演じようとして批判を浴び、降板したというケースが続きました。この議論についてはどう思いますか?
自分にはまったく似てない他人の視線を通じて、物事を見ることは必要だと思います。そうでないと、自分自身を狭いところに閉じ込めてしまうことになり、最悪の結果をもたらします。俳優の本質とは、別の人間を演じることができるということ。シスジェンダーの女性だからトランスジェンダーの役が演じられないのであれば、女優はパン職人の役も演じられないことになります。ジェンダーに閉じ込めることはよくない。しかも、そうした行為は、トランスジェンダーをトランスジェンダーの枠組みの中に押し込めてしまうことになりかねない。議論が起こること自体はとても良いことだと思いますが、極端に走るのは危険だと思います。多様性を重視しなければならないことは確かです。多様性こそが、社会を豊かにしてくれます。差違があるからこそ、社会は豊かなのです。
──ベルリン国際映画祭が、男優と女優の区別を撤廃して、俳優賞にするという発表に関してどう思いますか?他の映画祭や映画賞もそうなるといいと思いますか?
考え方としては、良いと思います。けれども……この”けれども”は強く言わせていただきたいのですが、私は、ここで女性がまた外にはみ出されるのではないかと恐れています。本当の意味での男女同数制がこれによって出来上がるとは思いません。おそらくその賞をもらう男優が、女優よりも多くなるのではないかと心配してしまいます。他のジャンルでもそうですが、女性は男性より頑張らないと出てこられないというのは事実です。なので、この後どういう風になるのか、賞の行方はどうなるのか、危惧しつつ動向を見守りたいと思っています。

──ところで、日本のアニメや漫画がお好きだそうですね。
はい。ジブリのファンで、『ハウルの動く城』が大好きです。『進撃の巨人』も大好きです。漫画で少し日本語を覚えました。学生時代も、先生が日本語をわからないことをいいことに、堂々と“バカ先生”って言ったりしてからかっていました(笑)。“愛している”という言葉も知っています。とても重要な言葉ですよね。
==

『MISS ミス・フランスになりたい!』(原題:MISS)
監督・原案・共同脚本/ルーベン・アウヴェス
撮影監督/ルノー・シャッサン
プロデューサー/レティシア・ガリツィン、ユーゴ・ジェラン
音楽/ランバート
出演/アレクサンドル・ヴェテール、イザベル・ナンティ、パスカル・アルビロ、ステフィ・セルマ
2020/フランス/フランス語/スコープサイズ/107分
日本公開/2021年2月26日(金)、シネスイッチ銀座ほか全国公開
配給/彩プロ
© 2020 ZAZI FILMS – CHAPKA FILMS – FRANCE 2 CINEMA – MARVELOUS PRODUCTIONS







