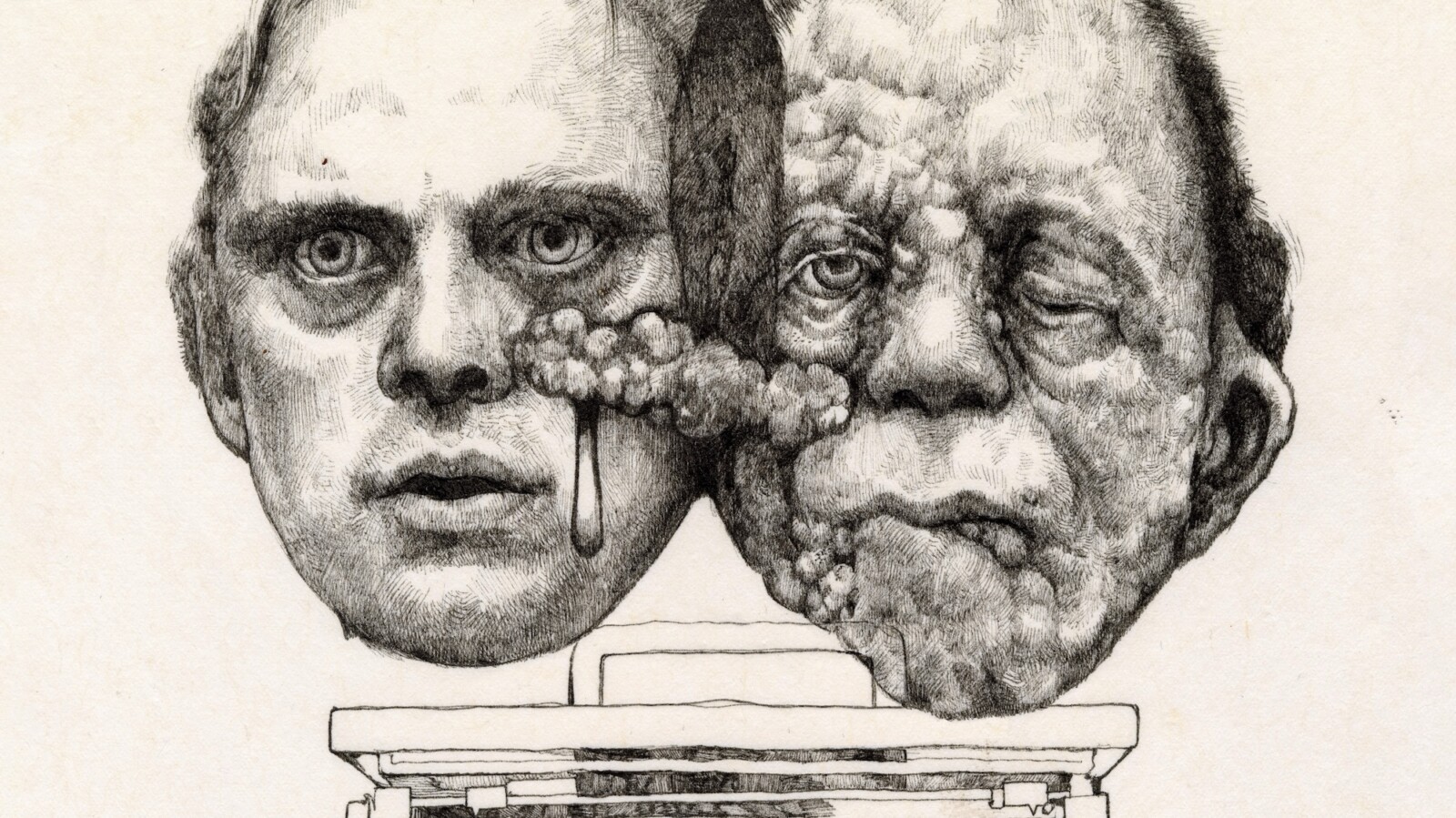【単独インタビュー】『ベイビーティース』シャノン・マーフィ監督が7年かけた長編デビュー作で証明したこと
- Atsuko Tatsuta
第76回べネチア国際映画祭を皮切りに各国の映画祭を席巻した『ベイビーティース』は、オーストラリアの新鋭シャノン・マーフィの長編デビュー作です。

余命を宣告された16歳の高校生ミラ(エリザ・スカンレン)は、駅のホームで青年モーゼス(トビー・ウォレス)と偶然出会い、恋に落ちる。素行の悪い彼をミラの母親アナ(エシー・デイヴィス)と父親ヘンリー(ベン・メンデルソーン)は嫌い、交際に反対するが、ミラは自分を特別扱いしないモーゼスと彼の刺激的な世界に夢中になっていく。やがて、両親は彼を家に住まわせ、娘の最初で最後の恋を見守ろうと決心するが──。
ミラ役にはグレタ・ガーウィグ監督の『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(19年)で三女ベス役を演じたエリザ・スカンレン、モーゼス役にはNetflixの人気シリーズ『ザ・ソサエティ』(19年)で米国ドラマに進出したばかりのトビー・ウォレスと、オーストラリア出身の新進俳優が主演に抜擢。ウォレスは、本作でベネチア国際映画祭マルチェロ・マストロヤンニ賞(新人俳優賞)を受賞し、注目を浴びました。
母アナ役には『欲望という名の電車』でローレンス・オリヴィエ賞を受賞したエシー・デイヴィス、父親ヘンリー役には『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』(16年)、『レディ・プレイヤー1』(18年)などのベン・メンデルソーンと、実力派が顔を揃えました。
本作が初監督作品にも関わらず、世界三大映画祭のベネチア国際映画祭コンペティション部門に選出され、米バラエティ誌の「2020年注目すべき10人の監督」にも名を連ねたシャノン・マーフィ。日本公開に先立ち、拠点としているオーストラリア・シドニーからFan’s Voiceのオンラインインタビューに応じてくれました。

シャノン・マーフィ監督 © La Biennale di Venezia – Foto ASAC
──『ベイビーティース』(19年)は、あなたにとって初の長編映画になりますね。これまではテレビや舞台で活躍されてきましたが、映画デビューに至った経緯は?
はい、この10年間はTVドラマと舞台の演出をやってきました。知り合いのプロデューサーからリタ・カルネジャイスの戯曲を紹介されました。舞台の公演はすでに終わっていたので鑑賞できなかったのですが、とても気に入りました。登場人物たちのキャラクターにはどれも繋がりを感じましたし、何よりも設定がとても興味深かったですね。病で死期が近い少女がいて、周囲の人たちがそういった状況に対して、どんな風に対応していくのか。彼女が目の前にいる時、あるいはいない時に、どんな振る舞いをするのか。
複雑で多様性にも富んだこの設定を、映画によってもっと掘り下げたいと思いました。まだ10代の若い人が死んでいくという深刻な話なのに、どこかユーモアや明るさがあるところも気に入りました。向き合っている現実が厳しいからこそ生まれるユーモアや明るさもあると思います。それを掘り下げるのは、興味深いこと。こういう物語を悲劇的に描くことは、作る側からすれば楽だと思うけれど、喜劇と悲劇が混じり合っている方が、本当の意味でリアルなのだと思います。
──戯曲から映画への過程でキーポイントになったところは?
私は舞台を観てないので、影響を受けすぎることはなかったと思います。戯曲で気に入ったのは、章立てでタイトルが付いているところでした。それぞれにまるで神が語りかけているようなタイトルが付いていたんです。例えば「賽を振りなさい」とか、「ダンス・ダンス・ダンス」とか。その章立ての構成は、映画でも踏襲したいと思いました。

──戯曲を読んでから7年間かけたそうですが、時間がかかった理由は?
リタ・カルネジャイスと一緒に脚本を書いていました。特に時間がかかったという理由もないのですが……良質なものをつくるのには、時間がかかると思います。それに、映画デビュー作をどうしようかとずっと考えていて、納得するものにしたかった。でも、十分に時間をかけた価値はあったと思っています。
──キャスティングが素晴らしかったですが、どのように俳優を選んでいたのですか?
ありがとうございます。普段から、リアルかつ自然で偶発的な演技が出来て、挑戦を恐れない俳優が好きです。それにもちろん、演技の技術力が高い人。すべて持ち合わせる俳優はなかなかいないんですけれどね。
実は俳優にとって、シリアスな演技はそれほど難しくないんです。でもこの作品には、ちょっと風変わりなコメディのようなトーンもあるので、コメディ的な演技力を持っていることも求められました。両親を演じたベンとエシーはベテラン俳優ですし、エリザとトビーは若いけれど、それなりの経験を積んでいて、実力があります。このような小さな作品は撮影に時間をかけられないので、俳優の技術力もとても重要なんです。

ベン・メンデルソーン、シャノン・マーフィ(監督)、エリザ・スカンレン、トビー・ウォレス(第76回ベネチア国際映画祭にて)© La Biennale di Venezia – Foto ASAC
──ベネチア国際映画祭で本作を観て、エリザに魅了されました。その後グレタ・ガーウィグの『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』も観たのですが、本当に素晴らしい役者ですね。彼女はどのように見出したのですか?
キャスティングディレクターがずっと彼女に目をつけていたんです。実は、ミラ役のキャスティングにはとても時間がかかりました。エリザも会ってすぐに決めたわけではなく、実際にオファーしたのは、オーディションから1年ほど経ってからでした。ミラはとても特別なキャラクターなので、どういう俳優に演じてもらうのが良いのか、私が見極めるのに時間がかかってしまったんです。通常、主人公は、まずそれまで生きてきた人生が描かれ、それから何か出来事があって変化していきますが、ミラの場合は冒頭2分で劇的な変化が始まります。それをどう描くべきか、私自身が見定めるまでに時間がかかったということ。つまり、私のせいですね。エリザは知的で自由で、役者としての幅があります。最終的には、たとえ私がどのように描こうとしても、彼女なら応えてくれるだろうと確信しました。

──ベネチア国際映画祭ではトビー・ウォレスが新人俳優賞を受賞したことでさらに注目が集まりましたね。
こんな小さなインディペンデント映画がベネチアのコンペに入っただけでもすごいことなのに、トビーの受賞は飛び上がるほど嬉しかったですね。いまだに頬をつねるような気持ちです。
──ベン・メンデルソーンは、『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』や『レディ・プレイヤー1』などで多くの人に知られる俳優ですが、今回はハリウッド大作での彼とは違う側面が見られますね。
ベンは、オーストラリアではコメディ作品で知られているとても達者な俳優です。もちろん最近では、ハリウッド作品での”ダークフォース”的なイメージもありますけれどね。今回は、父親役を演じるのが魅力的だったのだと思います。ヘンリーはコミカルな部分もありますが、内省的な役でもあるので、上手い役者でないと演じきれません。

父ヘンリー(ベン・メンデルソーン)、母アナ(エシー・デイヴィス)
──物語の多くがミラの家で展開されますが、デザインや間取りなど、この家はとても興味深かったです。あなた自身がデザインしたのですか?
いいえ。そうしたかったのですが、制作費が少なくて、撮影用に家を建てることはできず、ロケできる家を探しました。ミッドセンチュリーの家が良いと思っていると、プロデューサーのアレックス・ホワイトが、シドニーの郊外のセント・アイヴスで探してきました。女性パイロットが住んでいる家で、一度もリノベーションをしておらず、建てられた当時のまま維持されていました。クイーン・オブ・ザ・ナイト(月下美人)という植物のある美しいコートヤードがあったり、バックヤードもあって奥行きもあります。
愛情のある温かい家庭だけれど、ミラはあの家で閉塞感も味わっています。籠に閉じ込めた鳥のように。両親は彼女のことを守ろうとするけれど、それがミラの負担になってもいる。なので、広さと奥行きがありながらも、誰が何をしているのかがどこからでもわかるような、ある意味プライバシーの無いあの家の作りは、ミラと両親の家にふさわしいと思いました。この映画の重要な登場人物ともいえるので、あの家について質問していただいて嬉しいです。

──あなたは子ども時代、海外で暮らした時期も長かったと聞いていますが、どのようなアーティストに影響を受けてきたのですか?
まずはラース・フォン・トリアーですね。『奇跡の海』(96年)のサウンドデザインは、『ベイビーティース』に直接的に影響を与えているとも言えます。とても生々しくて、リアルなものを感じる音。今回は、同じようにADR(アフター・レコーディング)をせずに、鳥やコオロギの鳴き声とか、オーストラリアの夏のざわざわした音を活かしています。
カメラワークに関しては、ジョン・カサヴェテスがとても好きですね。『こわれゆく女』(74年)は、ミラの母親であるアナのキャラクター造形に影響を与えていると言えます。それから『君の名前で僕を呼んで』(17年)は完璧な作品ですね。あの映画が描き出す親密さがとても好きです。また、ドイツ映画の『ヴィクトリア』(15年)も好きです。全編ワンテイクで撮られた作品なのですが、監督が自分の力を見せつけるためにワンテイクで撮ったわけではなく、あくまでも物語のためにワンテイクを選択しているところが良いですね。
基本的に、有機的で自然な作品が好きですね。押し付けがましさを感じさせるものや、作為的なタイプの作品は苦手です。

──初長編を撮り終えて、ドラマや舞台との違いを感じますか?
演出家として舞台では10年、テレビドラマでは6年のキャリアがあります。映画とドラマの一番の違いは、ポストプロダクションにかける時間ですね。プリプロや撮影に関してはテレビドラマと映画はあまり変わりませんが、テレビは急いで作るので、仕上げにはあまり時間を費やせません。私は音や色彩なども納得がいくまで調整したいので、この差は大きいですね。最近、特にイギリスでは、ドラマでも制作費も多く使い、ポストプロダクションに時間もかけられるようですが。今、新たにイギリスのテレビシリーズに取り掛かっているのですが、プリプロもポスプロもじっくり時間をかける予定なので、映画に劣らないクオリティになると思います。
アーティストは作品を作るために、自分にはこういうことができると証明したり、自分が持っているアイディアを試行錯誤しながら周りに見せていく必要があります。初監督作である『ベイビーティース』が多くの人からポジティブな反応を得たことによって可能性が広がりましたし、自分でも自信を持てるようになりました。
==

『ベイビーティース』(原題:Babyteeth)
病を抱える16歳のミラは、孤独な不良⻘年モーゼスと出会い恋に落ちる。ミラの初めての恋を両親は心配し猛反対するが、ミラは怖いもの知らずで自分を特別扱いせずに接してくれるモーゼスに惹かれ、彼との刺激的でカラフルに色づいた日々を駆け抜けていく―しかし…
監督/シャノン・マーフィ
出演/エリザ・スカンレン、トビー・ウォレス、エシー・デイヴィス、ベン・メンデルソーン
2019年/オーストラリア/カラー/5.1ch/ヨーロッパビスタ/117分
日本公開/2021年2月19日(金)新宿武蔵野館、渋谷ホワイトシネクイントほか全国ロードショー
配給/クロックワークス、アルバトロス・フィルム
公式サイト
© 2019 Whitefalk Films Pty Ltd, Spectrum Films, Create NSW and Screen Australia