【単独インタビュー】黒沢清監督『スパイの妻』の主人公が女性の理由
- Atsuko Tatsuta
蒼井優を主演に迎えた黒沢清監督最新作『スパイの妻〈劇場版〉』は、太平洋戦争開戦前夜の日本を舞台に、運命に飲み込まれる夫婦の姿を描いた第一級サスペンスです。

1940年、神戸で貿易会社を営む優作(高橋一生)は、赴いた満州で偶然にも恐ろしい国家機密を知り、正義のため、事の顛末を世に知らしめようとします。妻の聡子(蒼井優)は、反逆者と疑われる夫を信じ、スパイの妻と罵られようとも、ともに生きることを心に誓います。正義、欺瞞、裏切り、愛──。
『CUREキュア』(97年)以来、『回路』(00年)では第54回カンヌ国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞、『岸辺の旅』(14年)では第68回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門監督賞を受賞するなど国際的評価を高めてきた黒沢清監督。『スパイの妻』は、ホラーやスリラーなどジャンル映画の名手が、初めて手がけた歴史劇です。
本作で、9月に開催された第77回ベネチア国際映画祭で銀獅子賞(監督賞)を受賞し名実ともに日本を代表する監督となった黒沢清監督が、Fan’s Voiceの単独インタビューに応えてくれました。

──ベネチア国際映画祭監督賞(銀獅子賞)おめでとうございます。
ありがとうございます。
──『スパイの妻』は、黒沢監督にとって初めての歴史ドラマですね。脚本は、濱口竜介さん、野原位さんとの共同執筆です。どのような経緯でこのプロジェクトは始動したのですか。
この話を最初に持ってきたのは野原なんです。神戸で8Kで撮らないか、と。僕が神戸出身というそれだけの話なんですけど。数年前に濱口が『ハッピーアワー』という作品を神戸で撮ったときに、野原は共同脚本でプロデュース的なこともやっていた。二人とも僕が芸大(東京藝術大学)で教えた生徒なんです。野原は監督専攻だったのですが、意外にもプロデュース能力があったんですね。で、“撮るのはいいけど、何を撮ればいいの?内容はそっちで考えて”ということで、彼らふたりが『スパイの妻』の脚本を出してきました。
──脚本が素晴らしいですよね。
僕もその脚本がよく書けていてびっくりしました。でも、本当にこれ撮れるの?予算いくらかかると思っているの?って聞いたら、わかりませんと言うので、ダメだこりゃと思っていた。絶対に実現しないよ、というのが僕の最初の感想だったんです。でも、そこからが驚きで、彼らはいろんな人脈で会社に話をもっていって、実現しちゃったんですね。
──その後、脚本に黒沢さんが手を入れたのですか?
濱口竜介と野原位が書いたものは、オリジナルでよくこんなストーリーを思いついたなというくらい、本当に素晴らしかった。セリフも本当によく書けていた。でも、長すぎるとか、憲兵をもっと怖くしてもいいんじゃない?とか、いくつかの点で僕が手を入れさせていただきましたけれど、8割方は二人が書いたものです。

──なにも知識を入れずにこの作品を拝観したのですが、実話がベースかと思いました。制作チームは、それは狙ったのですか?
実話ではまったくありませんが、現実に起こったいくつかの歴史的な出来事は踏まえていますから、実話であってもおかしくないように作ろうとは思っていました。
──この作品は歴史ドラマですが、黒沢さんのスリラーやホラーなどのテイストやテクニックが人間ドラマと上手く融合して、とてもオリジナルな作品になったと思います。
そうですね。濱口や野原の脚本もそれが狙いだろうというところはわかりましたし、僕もこの時代の雰囲気や、この時代ならではの個人と社会の関係を描きたいと思いました。もっと言えば、戦争という巨大な重苦しいテーマが裏にある企画ですが、同時に、サスペンスだったりメロドラマといった僕の好きなジャンル映画でもあって、こういうのは日本ではあまり見たことがない。でも、オリジナルストーリーとして発想すれば、そういうジャンル映画の面白さと重いテーマは必ず共存できるはずだと信じていたし、彼らも同調してくれて、今回それがやっと実現しました。
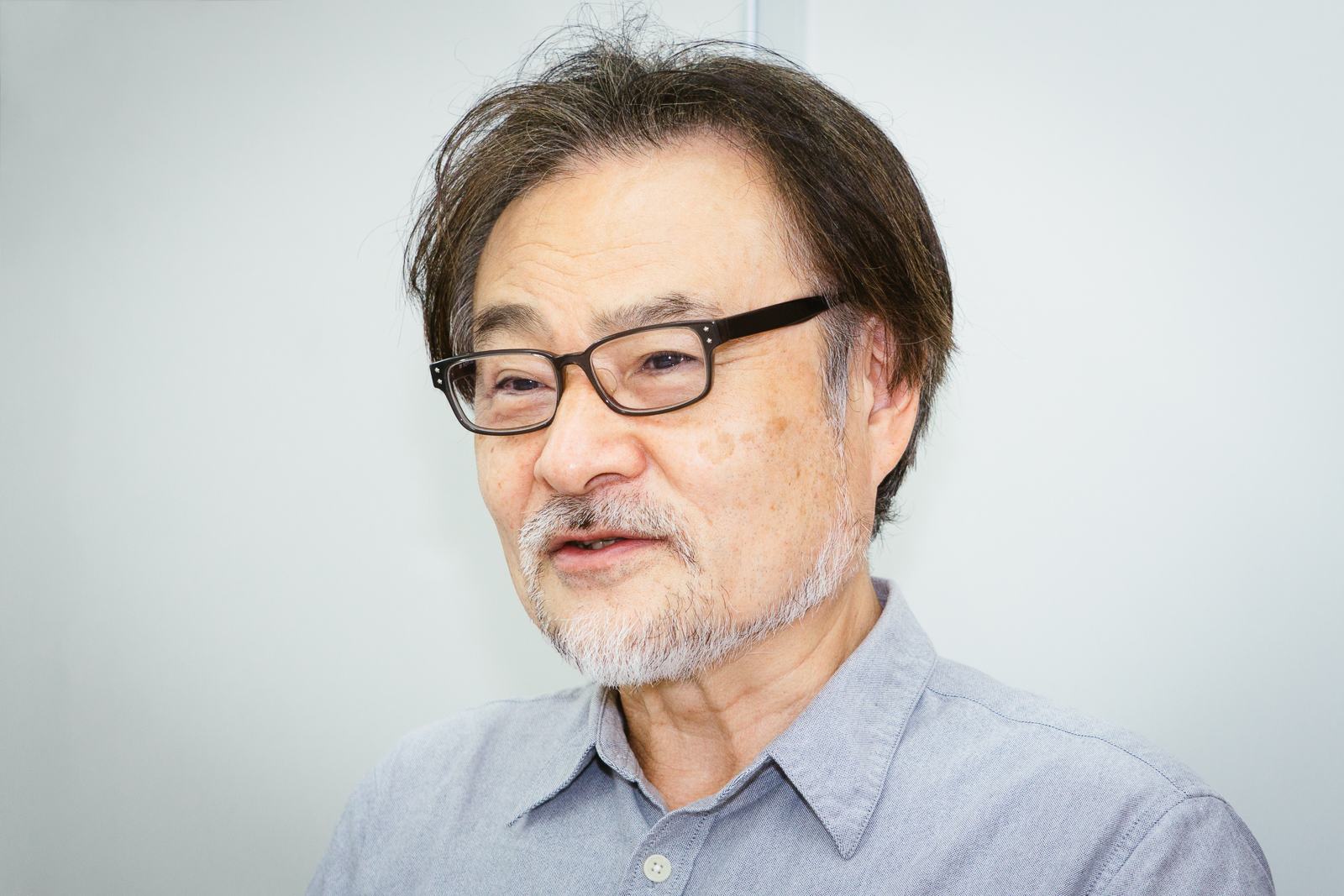
──NHKの8Kドラマとして撮って、それを劇場版映画に再編集したものがベネチア映画祭のコンペに選出されたわけですが、最初から映画祭は視野に入れていたんですか?
映画祭に関しては、狙うということはありません。全て運です。最終的にはベネチア映画祭に招待していただきましたけれど、TVドラマとして作ったものを選ぶかどうかは映画祭の判断ですから、こういう経緯のものでも選んでいただければ嬉しいなと軽い気持ちで応募しました。
──8Kでの撮影にはどういう魅力を感じたのですか?
僕は、依頼が来た仕事は基本的に断らないスタイルなんです。なので、”やってもいいですけど、8Kって何ですか?”というのがスタートだったんですね。正直、すごい技術だと思うんですけれど、本作のようなフィクションのドラマを8Kで作るのはなかなか大変なことだというのは、やってみてわかりました。ある程度の覚悟はしていましたが、やってみると、いやあ、大変でした。
──大変だったというのは、特にどの部分ですか?
撮影そのものは変わらないのですが、8Kはものすごくクリアで鮮やか。まさにそこにそのものがあるように見える。スポーツ中継とかはさぞかし素晴らしいでしょう。ということは、これが怖いんですが、俳優が演技をしているところを撮ると、俳優が演技をしているようにしか見えない。
──リアルに映り過ぎる?
はい。だから、ともすると俳優が演技をしているところを中継しているようにしか見えない。そこに一旦フィルターをかけて、俳優が演技をしていて、ある時代に優作と聡子がいて、という何かの変換が起こって初めて観ている側がふっと入り込めるようになるわけです。映画って、そうですよね。この微妙だけれど決定的な差を、どのように8Kで埋めていくのかが、正直、大変な作業でした。付け加えますと、画質をものすごくフィルムっぽくするとか、モノクロにするとか、ガサガサしたものにすれば、何やら生々しさは消えるのですが、そうすると8Kで撮る意味がなくなる。だから僕たちは、鮮やかできめ細かくて本当に臨場感があるんだけれど、フィクションとして成立しているという、ある意味矛盾したものを追求しました。そこはNHKの技術スタッフが本当に頑張ってくれて、驚くべきハイクオリティなものに仕上がったと自負しています。

撮影現場での黒沢監督
──映画は光と影の芸術と言われるくらいですが、8Kで“影”のアーティスティックな表現は可能なのでしょうか?
8Kの影は正直、いちばん難しかったです。というのは、真っ黒にすれば黒になるんですけど、そうではなくて暗い影の中に、“なにやらモノがあるような微妙な影”を8Kならではの技術で作り出そうとしました。ただ黒いだけではない、そこに何かがある感じ。それを狙いはしたのですが、全体の生々しさを殺していく技術との兼ね合いが実に難しく、微妙な暗さを出そうすると、暗いところにノイズが出る。何故かわからないんですが、デジタルの特性なんですかね。何かよくわからないものだとノイズになる。フィルムだとそういうことはない。
──制作費のことを考えなければ、フィルム主義の映画監督は結構いらっしゃると思います。デジタルとフィルムに対する考え方は、黒沢監督はどう思っていらっしゃいますか?
これはなかなかひと言で言いづらいんですが、僕はいつも、デジタルならデジタルで構わない。制作費が少ないこともありますが。逆に言うと、フィルムにも良いところもあるんですが、フィルムなら何でも良いってわけでもない。それは経験上よくわかっている。フィルムが良く見えるのは、何十年にも渡る試行錯誤によってすごい技術があるからです。よく知らない人がフィルムで撮ったら、そりゃ酷いものになります。それは8mmフィルムで嫌というほど経験した。おそらく、デジタルに(フィルムから)あっと言う間に変わってしまったので、技術を上手く受け継ぐ余裕があまりにもなかった。でも、今、ハリウッド映画でデジタルで撮った作品を映画館で観ても、昔のフィルム以上にフィルムのような古典的な光と影があって、言ってみれば19世紀絵画のようなものを、多くの監督が狙って撮っている。その絵画のようにしたいというのは、フィルムが何十年と積み重ねてきた古典的な美意識で、デジタルでも受け継がれていると思います。僕は、それがデジタルで出来るならば、デジタルで良いと思います。
──『スパイの妻』では、それが証明できたということですね。
そうですね。やれば出来るじゃん、ということですね。ただ、技術的にはやれば出来たという実感はあったのですが、内容に関しては、海外の方がこの作品をどう観るのかというのは、まったく未知数でした。海外の方が日本の歴史的なことをどれだけ知っているかわからないですし、日本映画というときに想像するものと大分違うだろうから、奇妙な作品とは思っても、この映画のサスペンスやメロドラマ性にどれだけ乗ってくれるか、わからなかったですね。それはそれでチャレンジだと割り切りましたが、ベネチアに行くことはできませんでしたけれど、海外の方もこの映画を楽しんでくれたと思うと、本当にやってよかった、信じていたものが実証されたという手応えはありましたね。

──キャラクターを作り上げるためには、かなりリサーチされたのですか。
いえ、あまりしていません(笑)。濱口たちの脚本に既に書いてありましたから。ただ、ひとつ言えるのは、当時、時代は戦争一色で、みんなそれに従って型にはまった生活をしていたと思われていますが、実はそうではない。表向きはそういうフリをして、人が見ていないところや心の中では、自由や楽しみを求め、より良い未来になんとか進んでいこうという、今の人と変わらない心情を持っていたはずです。優作と聡子は、時代に翻弄されはしますが、社会の状況とは別に、自分にはこういう夢がある、未来をこう進んで行きたいという、現代の人と変わらないはっきりとした心を持った人たちとして描きました。
──『スパイの妻』というタイトルの通り、この夫婦の妻の方に焦点が当てられています。近年、女性に対する価値観がドラスティックに変わっていると思いますが、その中で、女性の主人公をどう描こうと思ったのでしょうか。
近年、女性主役の方がなぜか多いんですね。現代劇であっても時代劇であっても、無言のルールのようなものがある社会で主人公が生きていて、そのルールに押しつぶされないし、逃げ出しもしない。ルールの中に留まりながら、自分を見失わず、理想に向かって進んで行こうとする主人公を描きたい。そうすると、自然と女性になっちゃうんですね。男は潰されるか、飛び出て行くかなんです。現代劇であっても、留まって潰されないというのは女性だよな…と。まあ、そんな責任を押し付けられる女性は迷惑かもしれないし、これはある種の男のロマンなのかもしれませんけど、でも僕の場合は、どうしても女性になってしまうんですね。

──今年のベネチアの審査員長はケイト・ブランシェットでした。映画祭の賞は、審査員団のメンバーによって評価も違ってきます。『スパイの妻』の聡子は、夫に寄り添う妻という立場で、自立したキャリアウーマンや革新的な活動家でもない。けれども、黒沢監督が今おっしゃったように、自分の与えられた環境の中で、自分の人生を生きていくという女性の強さや生き様を描いたこの作品を、審査員団が評価したというところにとても価値があると思います。単に強い女性が勝ち進んでいく、という物語ではない。
そう言っていただけると大変嬉しいですね。男であれ女であれ、周りの状況を打破してひとりで勝ち進んでいく主人公ってカッコ良いと思うし、アメリカ映画とかで描かれるそういうヒーローを観て良いなと思う時もあります。でも、周りの状況に従い、飲み込まれ、いろんな不自由を強いられても、柔らかく自分を守り通す。そういう人ってすごくない?って僕は思うんです。映画の主人公としては地味かもしれませんけれど。日本だからなのかもしれませんが、こういう価値観は女性を主人公にして描くとよりよく出せると僕は思っていたので、それをケイト・ブランシェットさんが目ざとく発見して評価してくれたのなら、こんなに嬉しいことはないですね。
──では、アメリカのヒーローものは苦手なのですか?
いえ、実は大好きです。それで育ったようなものです。こんな奴がいたら本当にいけ好かないという奴でも、観ていると応援してしまっているというのは、アメリカ映画のすごいところだと思うので、一観客として楽しんでいます。でも、男をなぎ倒していく女性が理想像だというのは、ちょっと違うかなと思いますね。単に敵をバンバンなぎ倒す男が素晴らしいヒーローと言えないのと同じです。

──次作の予定はありますか?
考えてはいますが、現状、すぐに進むのは難しい。まだ何も決まっていません。こういう時期はいつもあるんです。次回作準備中と言えば聞こえは良いですが、失業中ですね。
──『岸辺の旅』もそうでしたが、新作ごとに少しずつ角度を変えて撮り続けていらっしゃる印象がありますが。
それはそうですね。この歳になっても相変わらず、何か目新しいものをやりたい。前とまったく同じものをもう一回やってくれというのはなかなか辛い。最低一つか二つは、やったことがないからどうなるのかわからない、失敗したら大変だけどやってみようという、チャレンジする要素がないと、なかなか次に進めませんね。
──日本では新藤兼人監督は晩年まで作品を撮り続けましたし、海外だとクリント・イーストウッドやジャン=リュック・ゴダールなど、80代・90代で作品を撮っている人もいますよね。
いやあ、すごいですよね。素晴らしい先達たちが映画史上にはたくさんいますので、まだまだ先は長いなあ、と。まだ発展途上というのが実感ですね。
==

『スパイの妻<劇場版>』(英題:Wife of a Spy)
1940年、神戸で貿易商を営む優作は、赴いた満州で偶然恐ろしい国家機密を知り、正義のため、事の顛末を世に知らしめようとする。聡子は反逆者と疑われる夫を信じ、スパイの妻と罵られようとも、その身が破滅することも厭わず、ただ愛する夫とともに生きることを心に誓う。太平洋戦争開戦間近の日本で、夫婦の運命は時代の荒波に飲まれていく……。
出演/蒼井優、高橋一生、坂東龍汰、恒松祐里、みのすけ、玄理、東出昌大、笹野高史
監督/黒沢清
脚本/濱口竜介、野原位、黒沢清
音楽/長岡亮介
撮影/佐々木達之介
エグゼクティブプロデューサー/篠原圭、土橋圭介、澤田隆司、岡本英之、高田聡、久保田修
プロデューサー/山本晃久
アソシエイトプロデューサー/京田光広、山口永
制作著作/NHK、NHKエンタープライズ、Incline、C&Iエンタテインメント
制作プロダクション/C&Iエンタテインメント
2020/日本/115分/1:1.85
日本公開/2020年10月16日(金)新宿ピカデリー他全国ロードショー!
配給/ビターズ・エンド
配給協力/『スパイの妻』プロモーションパートナーズ
公式サイト
©2020 NHK, NEP, Incline, C&I







