【東京コミコン 2016】C.B.セブルスキーVS山崎理
日米カルチャー討論!

- Mutsuki
12/3(土)、第1回東京コミコンの2日目、14時20分より、アニメ監督の山崎理氏とマーベル副社長のC.B.セブルスキー氏の対談がステージにて行われた。
司会者による2人の簡単な紹介後、山崎監督の新作である『タイムトラベル少女』の紹介VTRが流され対談がスタート。
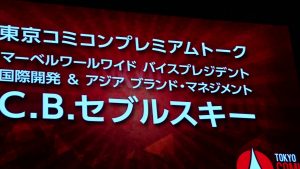
まず話したのがステージ裏トーク、2人の共通点。
子供の頃に日本のアニメや漫画を多く見て、さらに近年では日本人をコミックスの表紙に抜擢する‘マーベル・マンガ・ヴァリアント’を仕掛けたセブルスキーさん。幼い頃、日本製アニメがまだ少なく『宇宙忍者ゴームズ(ファンタスティック・フォー)』『シャザム』などアメコミ原作の輸入アニメに影響を受けた山崎監督。彼らは年齢も違うし、生きてきた場所も違う、だがお互いのポップカルチャーが相互に関係しあっていたという。山崎監督いわく、「僕より1つ上の世代がそれらに影響を受けてガッチャマンや破裏拳ポリマーなどを作った」とのこと。であるならば1990年以降に増えてきたと思われていたアメコミにオマージュを込めた日本の漫画やアニメは、それほど最近の話ではなく、むしろアニメの創生期からずっとあることで、そういう意味でアニメとアメコミにはスタイルの違いはあれど、決定的な違いは無いのかもしれない。

そして話はマーベルのアニメ展開『ディスクウォーズ・アベンジャーズ』について。山崎監督が「何故、実写で高い水準の映画が作れるのに日本人向けの手書きアニメを制作したのか?」と質問をぶつけた。するとセブルスキーさんは「日本人にマーベル・ユニバースを体感してほしい思いであの作品を制作した」と答えた。元々マーベル・ユニバースを生み出したスタン・リーは、ヒーローを身近な存在として描きたかった。そのためにDCコミックスのように架空の地名は使わず、あえてマンハッタンやニューヨークなど実在の地名を使用して、例えば、窓を開ければスパイダーマンがビルを伝っているのが見えるような親近感、すぐ傍にヒーローがいる世界(ユニバース)を作るのが目的だった。『ディスクウォーズ~』はその親近感を日本人に対し、日本で好まれているアニメという形で感じてほしくて制作した。もう一つ作品の素晴らしいところは日本では知られていないヒーローの活躍を描くこともあったかもしれない。アイアンフィスト、ローニン、デッドプールなどファンにしか認知されていないキャラクターをテレビに映すことで子供たちにアベンジャーズやX-MEN以外にも頼もしいヒーローがいることを伝えることができたのではないかと私は思っている。確かに子供向けということでパニッシャーなどダーティーなヒーローを出すことはできない弊害はあったが、多くのマーベルキャラクターが日本に認知されたのではないか。
セブルスキーさんいわく、忘れてはいけないのは「日本のアニメ、漫画もアメリカのポップカルチャーに影響を与えている」ということ。日本の作品がアメリカのポップカルチャーに与えた影響は計り知れず、1980~90年代にかけてアメリカで起こった漫画、アニメのムーブメントもそうだが、セブルスキーさんいわく「それ以前のガッチャマンやジャングル大帝からインスパイアされて作られた作品も多い。ギレルモ、ラセタ―などの今のアメリカを引っ張る代表的な監督たちも彼らなりの解釈と思い込みが反映されて素晴らしい作品が作られている」
ここで箸休め、セブルスキーさんが山崎監督に「好きなマーベル・キャラクターは?」。山崎監督は「アイアンマンは昔から好きだけどキャプテン・アメリカの映画を見てキャプテンが好きになってきた」と答えるとセブルスキーさんは「それは意外な事」だと返した。キャプテンはデザインやキャラクター性、精神など全てにおいてアメリカを体現している。その彼が日本でここまで支持されていることは嬉しい意味で想定外だったらしい。もうひとつデッドプールの人気は意外であること。続けて日本のファンに感謝までしてくれた。

セブルスキーさんが言うには「映画に限らずマーベルの作品はユーモアを取り入れることを重きにおいている。スタークやスパイダーマンのジョークのように。監督は何を重きにおいて作品を作るのか」。山崎監督は「笑顔になれること、そこで感動できて知識欲も満たせれば理想形」と答える。続けて「今、マーベル映画を見て興味を持つ対象がヒーローではなくテクノロジーに向かっていて、それが次回作への期待に繋がるのかもしれない」と話した。監督はアベンジャーズシリーズを指して「アニメでしか見せることが出来なかったものが実写で出来ることは、脅威であり憧れ」とも話していた。特に『マイティ・ソー』や『ドクター・ストレンジ』などファンタジーベースの作品ではどう観客を世界に引き込むかがカギとなる。だが実写で現実と幻想を同時に描くのが困難なのは、簡単に想像できるだろう。
その困難な点を近年のマーベル映画はクリアするだけではなく、さらに進化して私たちに提供してくれている。これはファンからすれば喜びであろうが監督のように作る立場の人間の視点に立てば自らもあのような作品を作らねばならない(作りたい)という使命感(願望)となり、‘脅威と憧れ’という言葉が現れたのかもしれない。
山崎監督が邦画の強みと弱みについての質問をした。アニメであれば吹き替えで新たにキャラクターを作ることができるが、実写では民族の多様性や日本語の限界が壁となり、日本人のみの世界で世界(グローバル)に戦いを挑めない。対してセブルスキーさんは冷静に強みと弱みについての見解を述べてくれた。
強みは、人間的な要素が強く観客が共感できるようになっていること。もうひとつに物語を語らせることができること。弱みは日本のみを考えて世界をおざなりにしている点。もっとグローバルな視点が無ければならないと語ってくれた。
最後にセブルスキーさんは日本のファンに対して「日本はクリエイティブな面では先進国なのだからもっと、世界にストーリーを語ってほしい、ファンとしてだけでなくひとりのクリエイターとして、もっと世界にインスピレーションを与えてほしい」と残してくれた。 では私たちはこの先何ができるのか、何をすべきなのか。ファンとして世界に発信するだけではなくクリエイターとして新しく作り出すこともこれからは求められるのかもしれない。そのようなことを考えさせられる対談だった。







